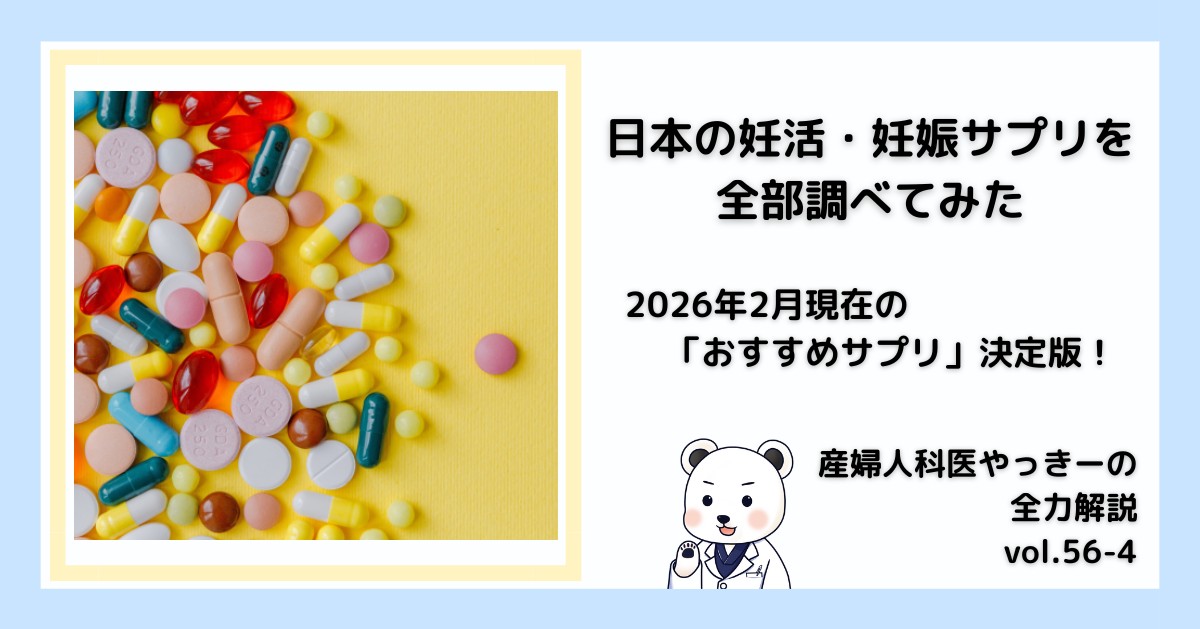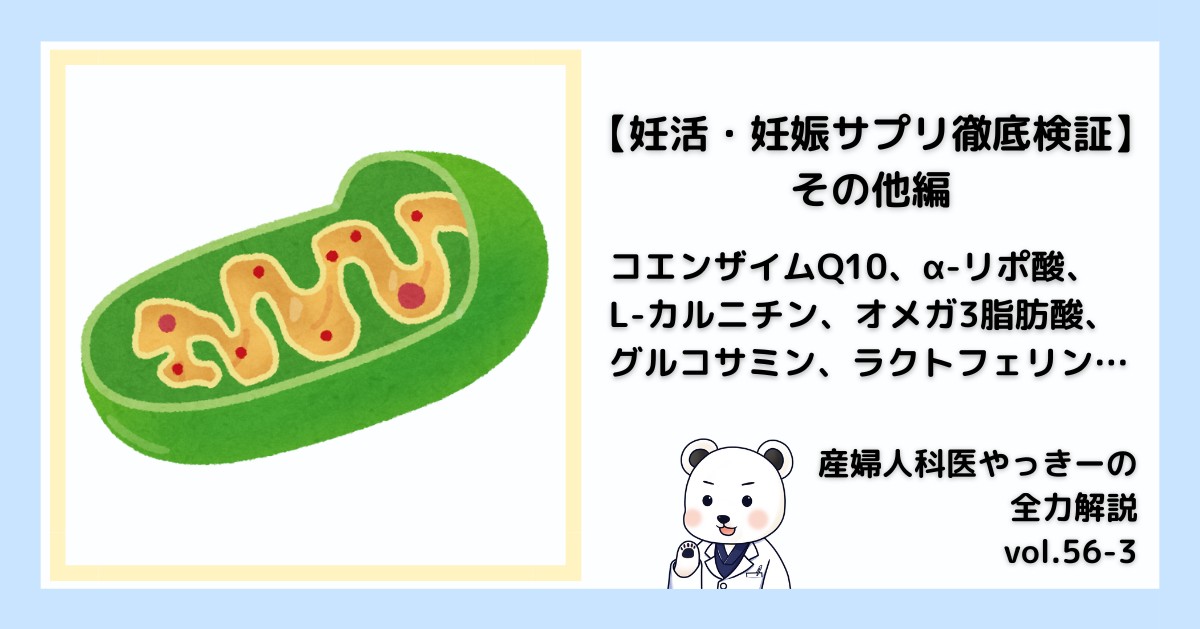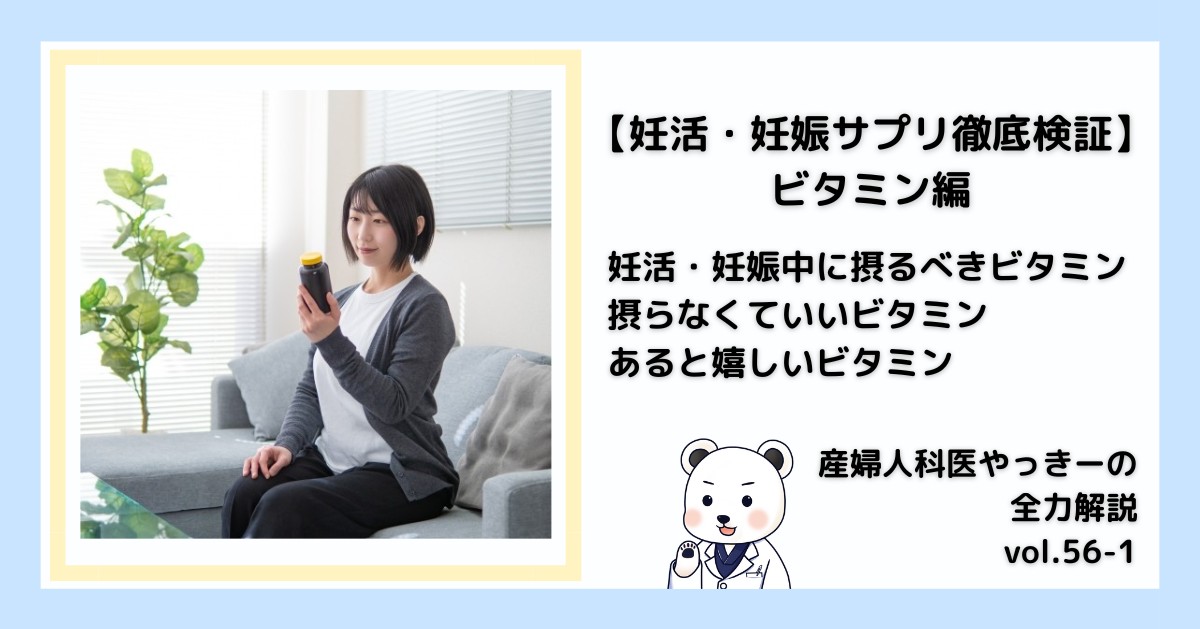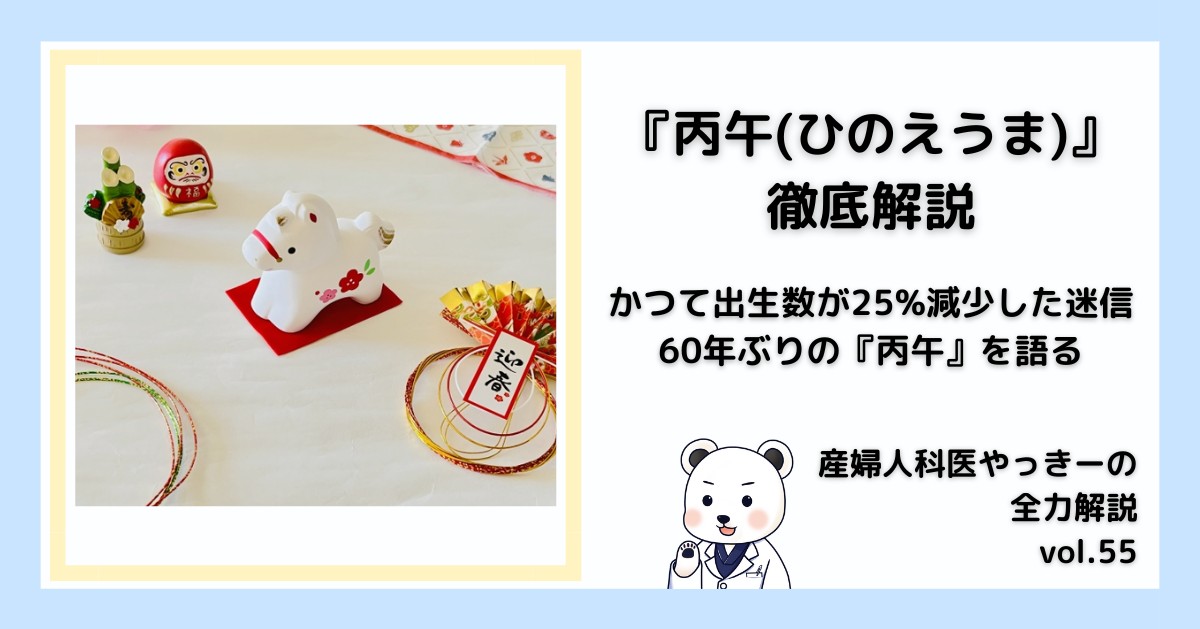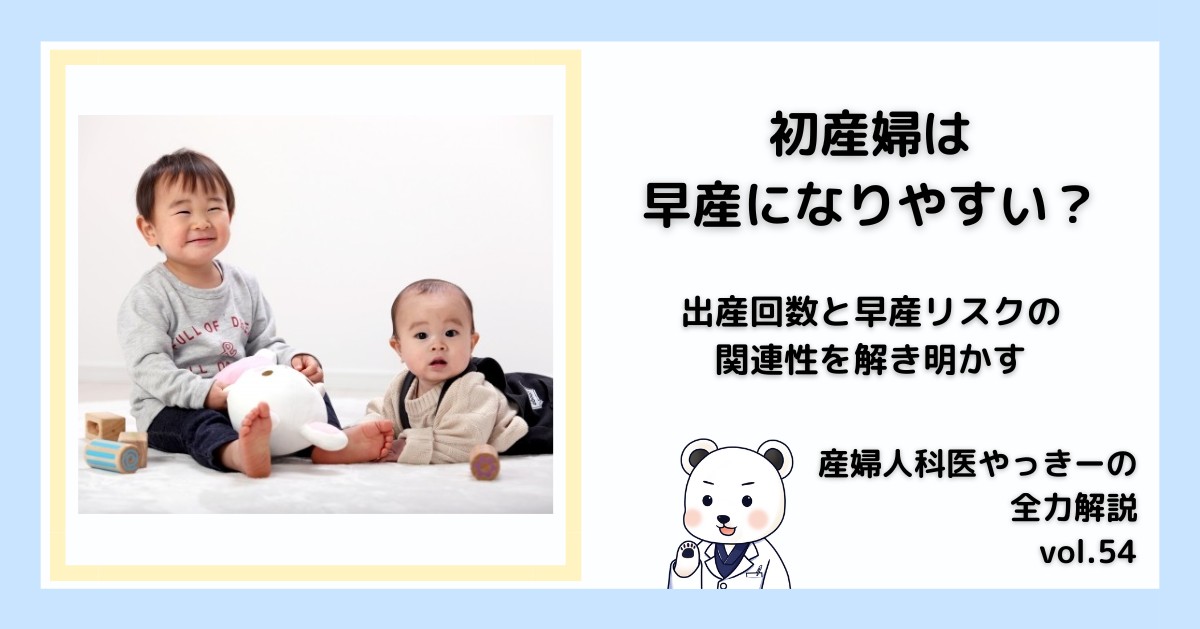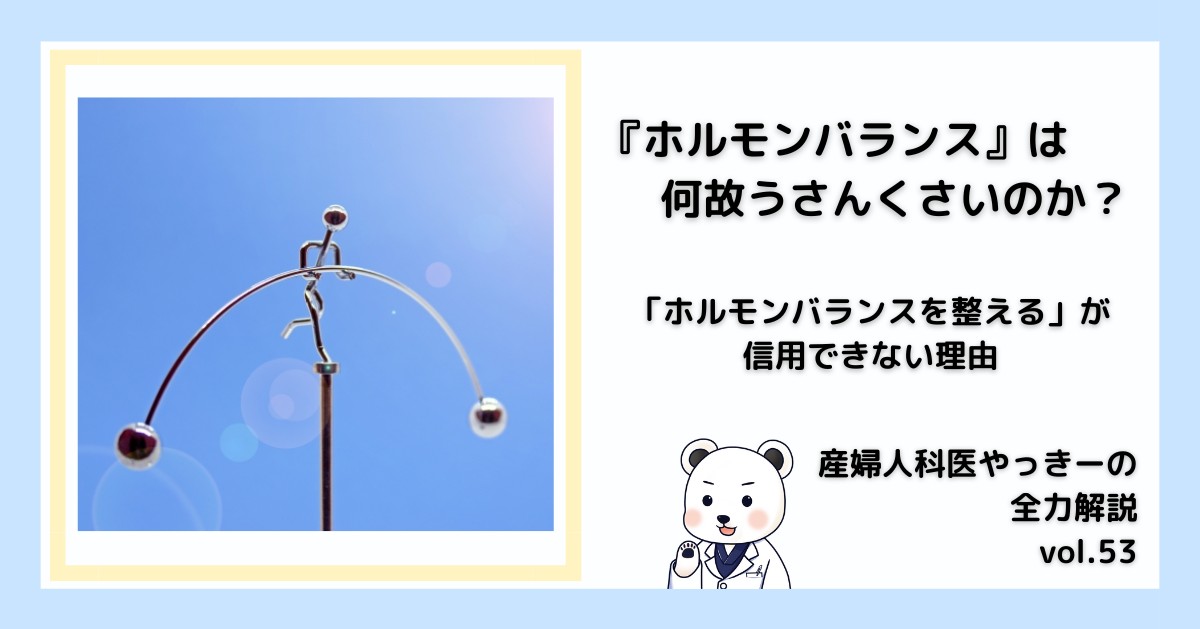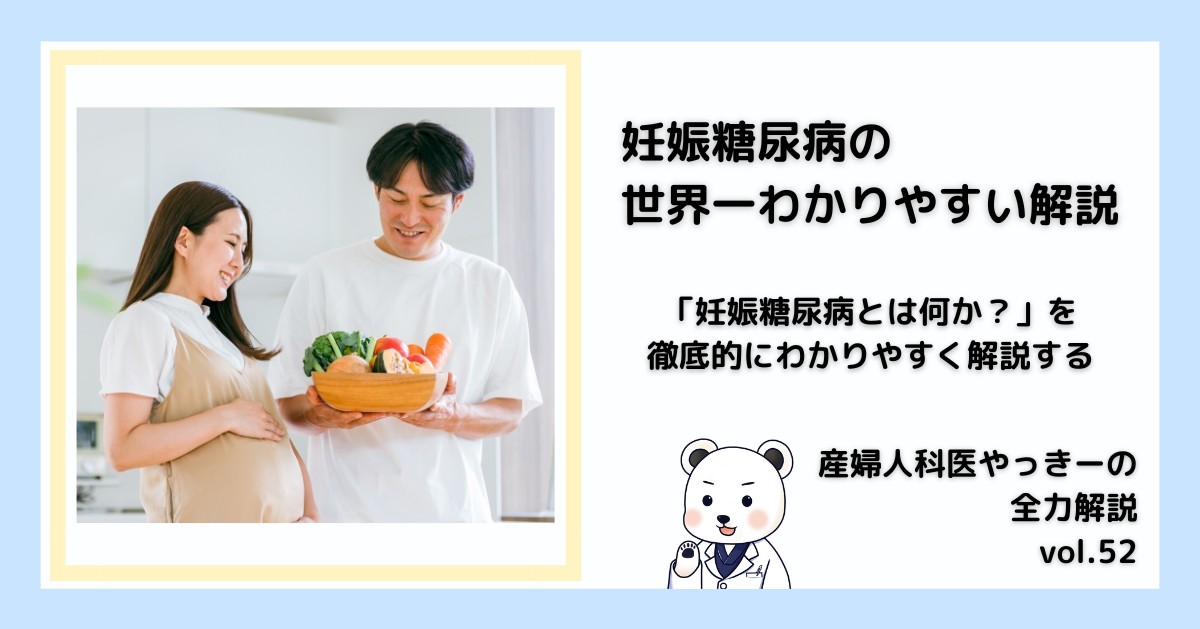全力解説 vol.26「ピルの話 上級編」

こんにちは!
産婦人科医やっきーです!
今回は「ピルの話 上級編」です。
以前、ブログで『NANA』で使われてたピルに関する解説をしたことがありますが、あちらが入門者向けの内容なのに対し、今回は「上級編」です。
まず最初に言っておきたいこととして、ピルは単なる避妊の薬ではありません。
ピルを適切に使うだけで日本が変わります。経済にも明確にプラスです。
これは何も産婦人科医のポジショントークというわけではなく、
日本において女性の月経に関する症状(生理痛やPMSなど)に伴う経済損失が年間約4900億円にのぼり、これを適切に治療することで年間約2400億円分の経済効果を生むということが経済産業省が令和2年に発表した報告書にも明記されています。
さあ!飲もう!低用量ピルを!
まずは産婦人科に行こう!!!
以上、怪しい宣伝おわり。
ここからはピルの歴史や俗説について、そしてピルの使い分けや最新のピル事情に至るまでを網羅した、「ピルの話 上級編」をお話ししていきます。

何で「ピル」って呼ぶの?
さて、そもそも「ピル」って名前は何やねん、と。
「Pill」は英語で「錠剤」を意味するため、冷静に考えると「ピルを飲む」というのは「錠剤を飲む」という意味でしかなく、その錠剤の中身については触れられていません。なにそれこわい🐻❄️
何故このように呼ばれているかというと、海外(英語圏)では経口避妊薬のことを「The Pill」と呼んでいるからです。
ザ・ピル。「これぞ薬の中の薬でござる」という威厳を感じずには居られません。
他のものに例えると、帝王切開のことを「ザ・手術」と呼ぶようなもんですね。これはこれで趣深いので、こんど隙があれば上司に「来週のザ・手術の件なんですけど」と話しかけて度肝を抜いてみたいと思います。

それはさておき、なぜ経口避妊薬が「The Pill」という名前で他との格の違いを見せつけているのでしょうか。
それは、経口避妊薬の波乱万丈の歴史が関係してきます。
まず、冷静に考えて飲み薬で避妊するって発想、なかなか凄まじくないですか?
コンドームやら腟外射精やらといった「精液を入れない」という発想は、まあ理解できる。
しかし現代の医学知識も常識もない時代に生まれたとして「飲み薬で妊娠を回避するんや!」という発想を果たして持てるでしょうか。私は自信ないです。
そんな常識外れの発明である経口避妊薬の構想は、アメリカの看護師・性教育者・活動家であるマーガレット・サンガー女史によるものです。
というかそもそもサンガー女史こそが「避妊」という言葉を作った人です。

彼女は20世紀初頭、貧困層の女性が頻繁に出産や流産をしている様子を見て、「そもそも妊娠を避ければええやんけ」という考えに至ります。
今では当たり前のこの考え方ですが、当時は「コムストック法」と呼ばれる法律によって「避妊法や避妊具を広めることはわいせつ行為にあたる」として違法行為扱いを受けていました。
なんやそのクソ法律は?と現在の価値観だと言いたくなるところですが、
当時は社会的な風潮として「避妊はフリーセックスを助長してモラルを崩す行為であるため、避妊に関する話をすること自体がドスケベハレンチ学園のToLoveるダークネスである」という考えが主流でしたし、
カトリックの教義では「結婚は神への協力、出産は神への貢献。よって避妊をする奴は神への冒涜!」とされていました。(そのため現在でも敬虔なカトリック国家では離婚が認められていませんし、中絶も違法扱いです)

サンガー女史の話に戻りますと、彼女はコムストック法にも負けず、貧困層の女性に対して避妊に関するパンフレットを配り続け、そしてコムストック法違反でがっつり投獄されます。しかも何回も。
それでもめげずに行った長年の活動が結実して「避妊」という概念を世に浸透させることに成功し、現在に至ったというわけです。
このようにサンガー女史は避妊法、ひいては女性の人権問題に関して素晴らしい活動実績を誇る一方で、
現在では差別行為として扱われている優性思想をがっつり持っていた人物でもあり、今では思いっきり大問題になる強制不妊手術なども支持していたため、
現在の価値観と照らし合わせて手放しに称賛できるわけでもない人間なのが扱いの難しいところです。
(いちおう彼女の弁護をしておくと、当時の過激派優生思想者たちが「不適合者は積極的に安楽死させろ」と主張していたことに関しては断固反対の立場をとっていました)
そんなサンガー女史ですが、1950年に生物学者のグレゴリー・ピンカス博士と出会い、
「女性が自分でできる確実な避妊法はないだろうか」と相談したところピンカス博士は「できるかもしれんで」と回答。

当時メチャクチャ有名人だったサンガー女史の口利きによってピンカス博士に多額の支援が集められたことで研究は猛スピードで進み、
2種類の女性ホルモン「エストロゲン(女性ホルモンその1)」と「プロゲスチン(女性ホルモンその2)」を配合することで排卵を抑制できることを突き止め、わずか4年で経口避妊薬の原型となる「高用量ピル」が完成。
コムストック法の煽りを受けながらも、産婦人科医のジョン・ロック博士の主導によりどうにか大規模臨床試験にこぎつけ、1956年に高用量ピルの有効性を証明しましたが、
やっぱりコムストック法が邪魔だったので1957年に月経の調節薬という名目で経口避妊薬・「Enovid」が発売されるに至ったのでした。(経口避妊薬として正式に承認されたのは1960年のことです)

出典:National Geographic
ただしこの当時の高用量ピルですが、「高用量」と付くだけあって今の医学では信じられんくらい大量のホルモンが配合されていまして、
現代で主流となっている低用量ピル・超低用量ピルはエストロゲンが20~35μgくらい、プロゲスチンは0.1~3mgくらいとなっているのに対し、
Enovidに含まれているエストロゲンは150μg、プロゲスチンは9.85mgにのぼります。
そのため、1956年当時の臨床試験では吐き気・頭痛・血栓症などの副作用もけっこう報告されていましたが、時代が時代だっただけにあんまり気にされず発売にこぎつけられてました。(今だと普通に問題になります)
しかし発売後、案の定というか1960年代に高用量ピルによる血栓症問題が顕在化(特にタバコを吸ってる女性)し、安全性が見直されることとなり、
加えて避妊目的にしてもこんなにたくさんのホルモンは要らんかったことが分かると少しずつ用量が下げられ、現在の薬剤設計に落ち着いていきます。

こうして安全性が確立されると同時に、当時の女性解放運動の熱の高まりも相まって「経口避妊薬は女性に自主的な生殖選択を与えるもの=女性の人権を守るもの」という風潮へと変化していき、
ついに経口避妊薬は「The Pill」としてその立場を確固たるものにしたわけです。
経口避妊薬が「ピル」と呼ばれるに至るには、女性たちや薬学者たちの苦難の歴史があったわけですね🐻❄️
ピルの導入がめちゃくちゃ遅れた日本
このようにして1960年にアメリカでピルが避妊薬として承認されると、他国も追随していきます。
イギリスは1961年に既婚女性を対象にピルを承認し、1967年に未婚女性にも解禁。
西ドイツも1961年に承認しています。
ただ、前述したようにカトリック教徒の多い国では「避妊薬」が教義上受け入れ難かったため、
イタリアでは1971年に承認、アイルランドは1980年代に法律が緩和され始めるなど、少々遅れての導入となりました。
そんな中、日本はというと1999年に承認。
カトリック諸国と違って宗教的規制があるわけでも何でもないのに、アメリカから約40年遅れでの承認です。

このあたりで性活動家の皆様は肩を温め始めているかもしれませんが、
実際には1960年から日本でも高用量ピルが月経困難症などの治療目的で処方できるようになっておりまして、
1971年に田中角栄首相(当時)が「安全性に疑問が残るので現段階では避妊薬として認める考えはない。ただし医師が自己責任で処方するのは法の禁ずるところではない」という旨の答弁をしました。
この発言がある意味で免罪符として働きまして、建前としては避妊目的は未承認だけど、医師の裁量で使う分には黙認、というどっちつかずの状況が続いていたわけです。
やっきー父(1980年頃から現役で産婦人科医)によると当時もそういうグレーな感じで普通に使われてた、というかそうやって使わざるを得なかったとか。
それでも1980年代には海外の臨床データも十分に蓄積し、1986年に国内での大規模臨床試験も行われ、いよいよ承認目前か…と期待されたのですが、
折しも当時、世界的に流行していたHIV/AIDSに対し「感染拡大を防ぐためには積極的にコンドームで避妊すべき」と叫ばれていたことが影響し、
当時の厚生省は「ピルを承認してコンドームの使用率が下がるとHIVの感染が拡大するおそれがある」としてピルの承認を延期。

まあでも当時のエイズに対する社会的風潮を考えると仕方ないのかも…?という雰囲気もありつつ、悪い意味で日本らしい何ともあやふやな扱いでピルが使われ続けていたわけですが、
1998年に男性向けの勃起不全治療薬であるバイアグラが申請からわずか半年で承認になったことで世論をビンビンに刺激。
「女性による自主的な生殖選択権よりも男どものチンコが勃つか勃たんかの方が大事なのかオラアアアアアアア」と当時の性活動家の神経を逆なでする結果となってしまい、日本でも1999年に低用量ピルが正式な承認に至ったのでした🐻❄️
(※ちなみにバイアグラの承認の背景には、持病がある人や用法・用量を守らずに内服するとメチャクチャ危険な薬であるほか、当時個人輸入で勝手にバイアグラを飲んでえらいことになった例があったことも関係しています。1997年にブランデーでバイアグラ5錠を一気飲みして救急搬送された江頭2:50さんとか。加えて個人輸入の弊害としてまがい物も出回っていたため、政府としてはちんちんが心配だからというより国内で正式に認定しないと人が死ぬから正規品を流通させたい意図があったわけです)
ピルに関する俗説
というわけで、長かったピルの歴史の話はここまで。
こういった紆余曲折を経て日本でも低用量ピルが使えるようになったわけです。拍手🐻❄️
そんなこんなで低用量ピルというのは非常に優れた避妊薬であると同時に婦人科疾患の治療薬でもある、そして経産省からも年間2400億円規模の経済効果が期待される非常に優れた薬なわけですが、
「危ない薬なんじゃないの?」「なんかよくわからんけど怖い」というイメージは尽きません。

ここでざっくりと、よく言われる俗説について見解を述べていきましょう🐻❄️
・ピルは副作用が強くて危険なのでは?
ピルにおける最大の副作用は「血栓症」です。
確かに、ピルに関する知見が整ってなかった頃は血栓症がしばしば起きてましたが、
「40歳以上」「BMIが30以上」「喫煙中」など、血栓症を起こしやすいリスク因子は既に特定されています。
よっぽど適当に診療をしてる医者ならともかく、一般的な産婦人科医ならリスク因子の数や強さに応じてピルを処方せず代替案をとることも多いので、
きちんと診察を受けた上で「この人ならピルを出しても大丈夫だろう」という判断をされたなら基本的には問題ないでしょう🐻❄️
(稀にヤバすぎるオンラインクリニックが適当にピル出して問題になってますがそれはまた別の話)
そもそも「ピルを飲んだら血栓症」というのはあくまでも相対リスクが上がるだけの話で絶対リスクが高いとは言えず、
ピルを飲んでいない人が血栓症を発症する確率は年間1万人につき1~5人程度、
ピルを飲んでいる人は年間1万人につき3~9人程度です。
ちなみに妊娠中の血栓症発症リスクは年間1万人あたり5~20人、
産後に至っては年間1万人あたり40~65人です。
結論として、ピルの内服によって血栓症を引き起こすリスクは妊娠中や産後よりもずっと低く、
もちろん注意はすべきですが「血栓症を避けるためにピルを一切使わない」というのも少々、筋が悪い選択と言えるかと🐻❄️
・ピルを飲むと将来妊娠しづらくなるのでは?
デマです🐻❄️
ピルの服用を中止すれば、次かその次の周期にはほぼ排卵が復活します。
むしろ、子宮内膜症や子宮筋腫といった不妊症にかかわる疾患がある場合、それらの進行を食い止める効果もあるので、
妊娠率の向上に関与こそすれど妊娠しづらくなることは考えにくいです。
・生理を止めるのって体に悪いのでは?
デマです🐻❄️
たまに頭の悪い自然派のデマ屋が「生理はデトックスである」みたいなオモシロ発言(高度貧血に至る過多月経の人にも同じこと言えんのかな)を繰り出してリテラシーのある皆様からの失笑を誘いますが、
生理は単に妊娠の成立しなかった子宮内膜を排出する現象にすぎません。
現在、日本で使用できるピルの種類
それではついに本題。
日本で使用できるピルにはどんな種類があるのか、それぞれどのような使い分けがあるのかを解説していきましょう。
現在の日本で販売されているピルは細かいものも含めて15種類くらいあり、「どれを選べばいいのかわからん」という問題がありますし、
なんなら現在内服されている方であっても「なんか分からんけど産婦人科で出されたやつ飲んでる」という方も少なくないはず。
ここで意識すべき区分は、「エストロゲン(女性ホルモンその1)の用量による区分」「プロゲスチン(女性ホルモンその2)の世代による区分」「相による区分」の3種類です。
ちと面倒くさいですが、これさえ押さえておけばご自身に合ったピルが選べるんだぜ🐻❄️

提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績