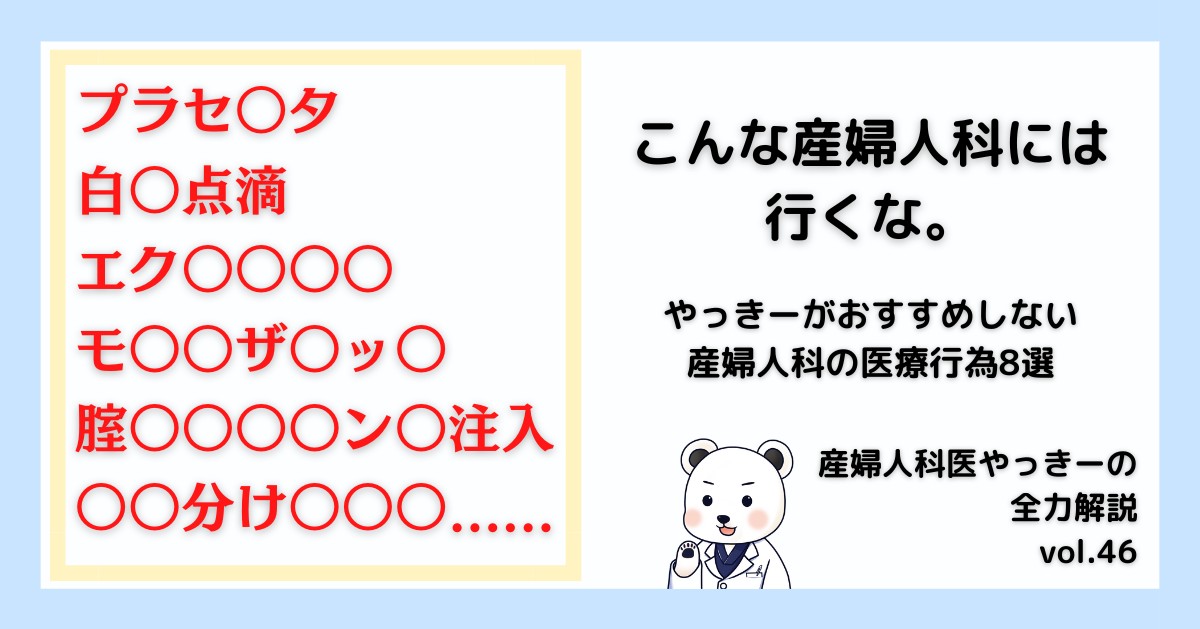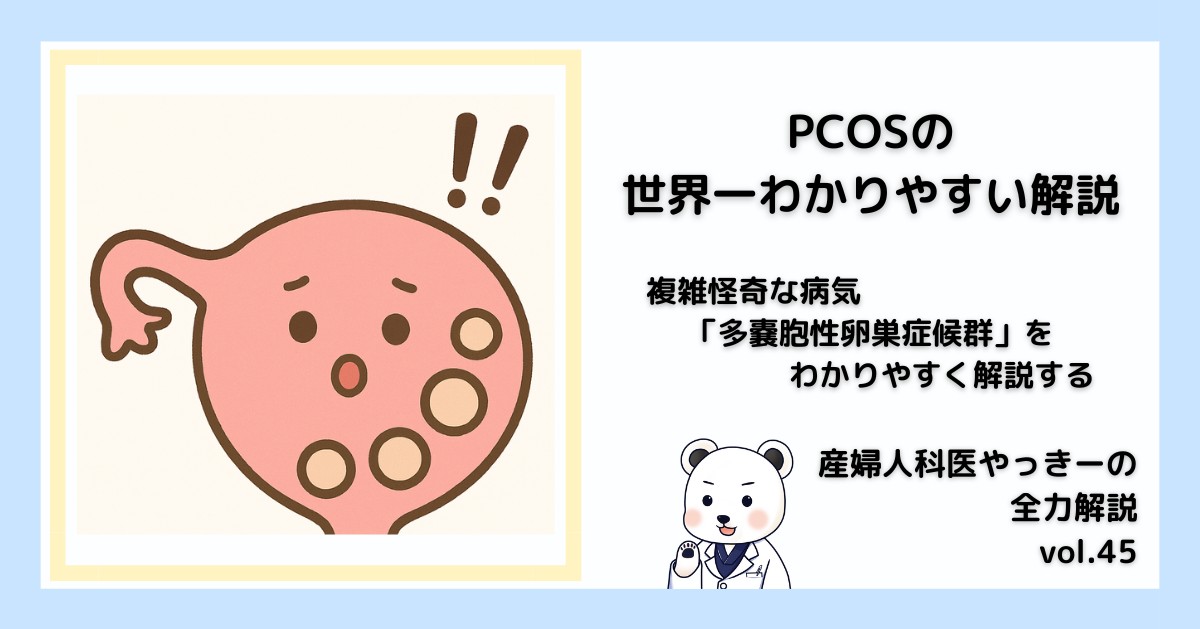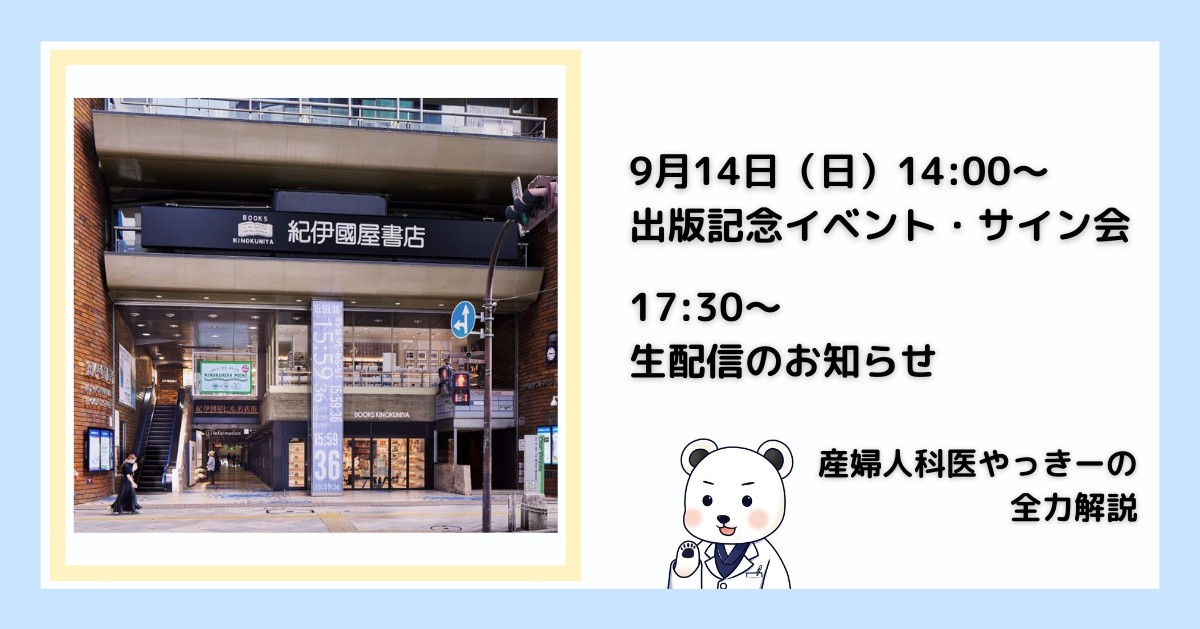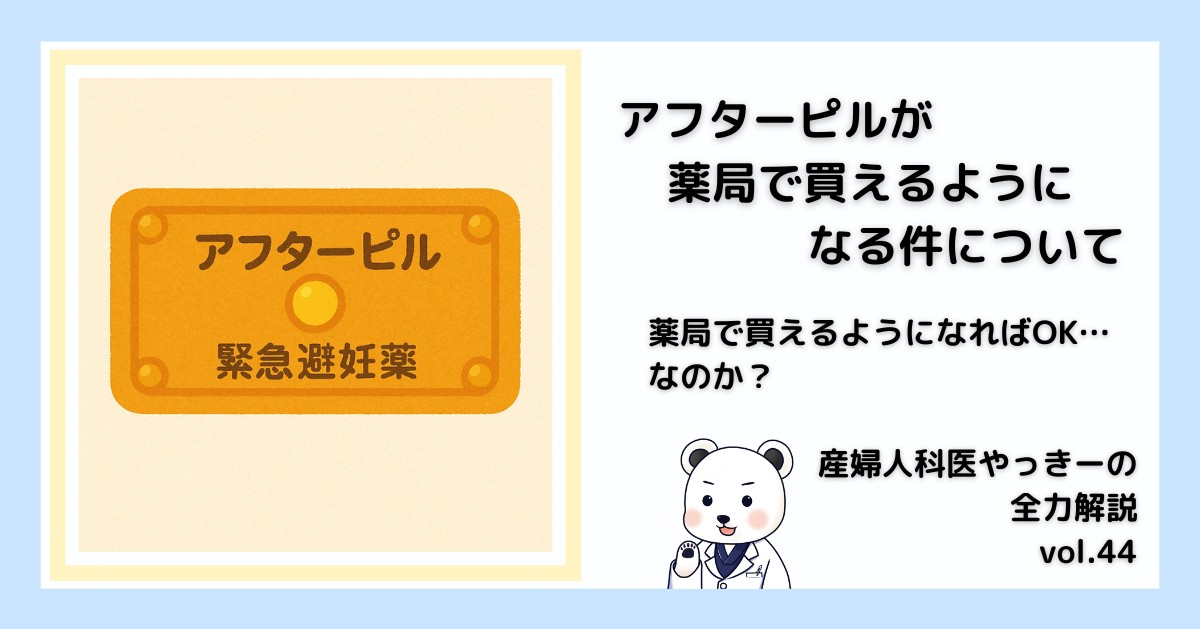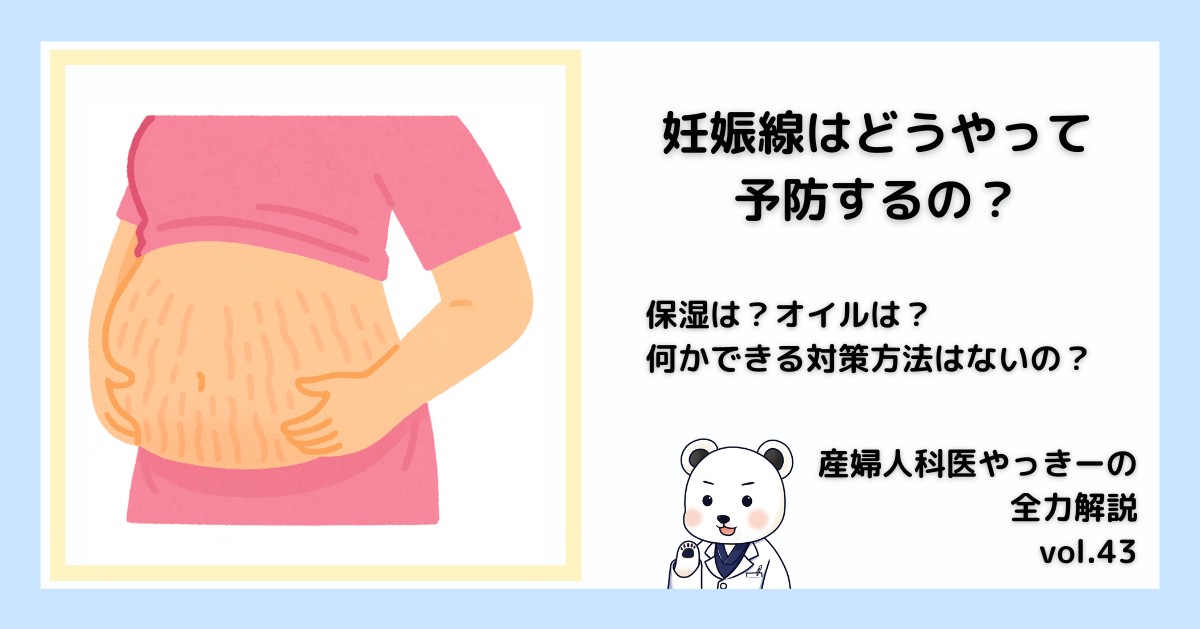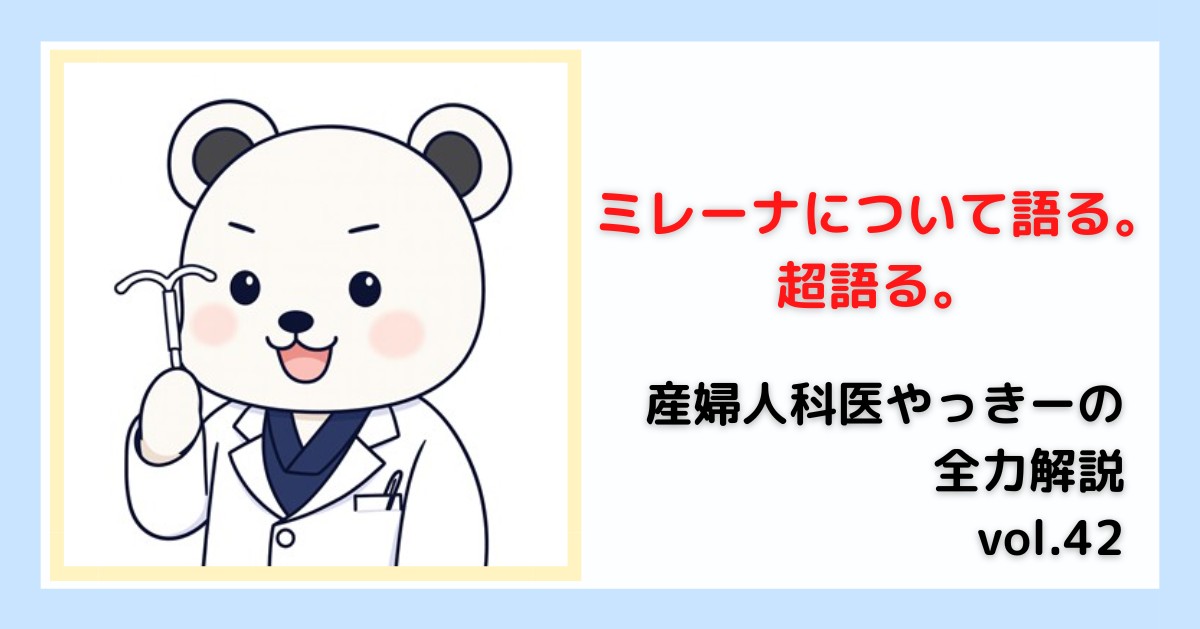全力解説 vol.34「結局、STAP細胞はあるの?」

こんにちは!
産婦人科医やっきーです!
2025年4月27日に放送された、TBS系日曜劇場「キャスター」第3話にてSTAP細胞騒動を思わせる内容のドラマが作られ、話題となりました。

出典:Yahoo!ニュース
まあ、このニュースに関してはどちらかと言うと女優・のん(能年玲奈)さんの地上波ドラマ復帰の方が主な話題となった感がありますが、
あの当時の騒動を大学病院で見ていた立場としては「アレがドラマになるのか…🐻❄️」と感慨深いものがあります。
ということを妻(医療従事者ではない一般人)と話していたところ、このような疑問をぶつけられました。
「STAP細胞って結局あったの?」

ままままじか!?🐻❄️
と思いましたが、妻にとっては「当時はニュースを見ても何が何だかよくわからなかった」とのこと。
まあ確かに、STAP細胞が何たるかを理解するためにはけっこう下地となる知識が要りますが、マスコミからのそのへんに関する言及はほぼ無しで割烹着やらリケジョやらありまぁす!やらが取り上げられまくって消えて行ったため、「結局アレは何だったのか」となるのはやむを得ないことです。
というわけで本日のテーマは「結局、STAP細胞はあるの?」です。
先にネタバレをしますが、STAP細胞はありません。
ただ「ありません」で終わっても面白くないので、せっかくなのでアレが当時の医療従事者から見てどれだけインパクトのある事件だったのか、なぜSTAP細胞が存在しないと断言できるのか、
そして山中伸弥先生がノーベル賞を取ったことでおなじみのiPS細胞(こっちはあります)がいかに画期的な発明なのかを解説していきましょう。
ちなみに私は細胞生物学や幹細胞医学の専門家というわけではありませんが、医大当時のゼミではiPS細胞をテーマにしていたためSTAP細胞騒動はかなり前のめりで見ていたクチですので、そこそこ温度の乗った感想がお伝えできるはず🐻❄️

幹細胞について
さて、STAP細胞の話をする前に「アレがもし本当だったらどれだけ凄い発明だったか」「当時なぜアレが爆発的に持て囃されたか」を解説せねばなりません。
決して「リケジョ」の物珍しさだけで取り上げられたわけではないのです。
そのために、まず解説したいのが「幹細胞」です。
まずご存知の通り、人間というのはたった1個の受精卵から始まります。
この受精卵が細胞分裂を繰り返し、この細胞は血液になり、この細胞は脳になり、この細胞は皮膚になり…といった感じで増殖することにより、最終的に一人の人間ができあがるわけです。

出典:再生医療ポータル
これは成長してからも同様で、たとえば皮膚が傷ついた場合には皮膚の細胞が分裂してスキマを埋め、元通りに修復しようとします。
ここで出てくるのが「幹細胞」です。
皮膚が傷ついた場合を例にとると、皮膚には何種類かの幹細胞が存在し、
「一番外側の皮膚担当」「ちょっと内側の皮膚担当」「皮下脂肪の担当」といった感じの役割分担が決められており、それらの幹細胞が適切に増殖することで傷が修復されるわけですね🐻❄️
この幹細胞ですが、ある一定の段階で役割分担が決定してしまい、元には戻りません。
我々の体の細胞にはすべて同じ「DNA」がありまして、DNAの中には体中のあらゆる細胞になれる設計図が内包されているわけなのですが、
「この細胞は皮膚の細胞」「これは肝臓の細胞」といった感じの役割分担がひとたび与えられると、それ以外の設計図はすべて封印されます。決して開かない引き出しに入れられるような感じです。

よって、我々の皮膚の細胞をどれだけ探してもそこから肝臓になれる細胞は採れません。
これは別にケチでそうやっているわけではなく、不要な設計図は仕舞っておいた方が効率が良いからです。
仕事の引き継ぎを受ける時、絶対使わないどうでもいい書類と一緒に極厚の引き継ぎ書を渡してきた奴にはSTF(ステップオーバー・トーホールド・ウィズ・フェイスロック)をかけてよいと日本国憲法で定められていますし、
こういう無駄な情報は少なくしておくに越したことはありません。

出典:毎日新聞
そんな中で、「それじゃ今後、皮膚の細胞分裂はこんな感じでシクヨロ。こっちの書類?いらんいらん、どうせ俺ら肝臓の細胞にならんし。必要なところだけこれに書いといたから」
と2ページくらいに仕様をまとめておいてくれれば「しごできパイセン…!🐻❄️」と感動にむせび泣いてしまうはずです。
この仕様の影響で、我々の体のどこをどう探しても「体中のどんな細胞にでもなれる細胞」=「全能性幹細胞」は存在しないため、全能性幹細胞を取り出すことは不可能です。

しかし。しかしです。
もしも「体のどんな細胞にでもなれる細胞(全能性幹細胞)」が採れたら、コレめちゃくちゃ応用がききません?🐻❄️
もし今後、何かの理由で私の肝臓がぶっ壊れたとしても、皮膚の細胞を採取してそこから肝臓の組織を再現することができるようになった…としたら、これはもう凄まじい医療革命です。
現在では臓器移植をする際に、臓器提供者の負担や拒絶反応のリスクもあるわけですが、患者本人の全能性幹細胞によって作られた臓器であればそれらもクリアできます。

それだけではありません。
何らかの新薬が発明されたとして、人体に直接試すのはリスクがあるな…と思われた場合も、
人工的に臓器を再現することができれば実験室の中だけで薬の効果や副作用を調べることも可能です。
産婦人科領域に関しても、何らかの理由で精子や卵子が採れない方が子どもを授かれる希望となり得ます。
こいつぁスゲェ🐻❄️
もはや医学を志す人間にとっては海賊王が遺したアレくらいの存在感と言って過言ではなく、ありったけの夢をかき集めて探しに行く価値のあるもの、それが「全能性幹細胞」だというわけです🐻❄️

出典:フジテレビ
ES細胞
せやかて工藤、そんな便利な細胞があったら大変なことやで、と思われるかもしれませんが既にあります。それも25年以上前から。
それが「ES細胞」です。
先ほど「幹細胞はある一定の段階で役割分担が決定してしまう」と書きましたが、
その「ある一定の段階」の手前の細胞を取り出してみると、どうでしょうか?
受精卵が細胞分裂を繰り返すと、「のちに胎児の体になる細胞」と「のちに胎盤になる細胞」の2つに分かれます。
ここで、前者の「のちに胎児の体になる細胞」を取り出すことで、「肝臓にも皮膚にも、何にでもなれる細胞(胎盤にだけはなれない)」になるわけです。

出典:Stemcell Knowledge & information Portal
…と、この作り方を見ると分かる通り、ES細胞には大きな弱点があります。
それが「のちに赤ちゃんの体になる予定だったものを壊している」という点です。ハッキリ言って倫理的には完全アウトです。
人間のES細胞が発見されたのは1998年のことですが、この研究があまり無制限に行われるとかなり世紀末なので、2001年にアメリカのブッシュ大統領(当時)が「人間のES細胞を新しく作るなよ?」と念押ししたほどです。
そのため、既に存在するES細胞を絶やさないように培養することで研究が続けられていました。
ちなみに「全能性幹細胞」は「体中の何にでもなれる細胞」を指しますが、
ES細胞に関しては胎盤にだけはなれないので「多能性幹細胞」と呼称されます🐻❄️
(胎盤をどうしても作りたい!という場面はかなり限られるので、ここはそれほど問題になりにくいですが)
iPS細胞
そんな感じで、ES細胞はちょっと使いにくいなあ…という状況を一変させた奇跡の発明が、京都大学の山中伸弥先生の「iPS細胞」です。

出典:京都大学
細かいところをすっ飛ばして解説すると、山中先生は皮膚の細胞にちょっと特殊な加工を施すことによって「ES細胞の性質にすごく似た細胞」を作り出すことができたのです。
設計図のたとえを使うとすれば、それまで固く封印されていた「使わない設計図」を取り出すためのカギを見つけた、というイメージですね。

このES細胞そっくりの細胞は「人工多能性幹細胞」、英語で「induced pluripotent stem cell」と呼ばれます。
頭文字をとれば「IPS細胞」となるところですが、当時は音楽プレーヤーのiPodが空前絶後に流行っていたため、山中先生はiPodにあやかって「iPS細胞」と命名しました。
(iPS細胞の命名から約20年が経ち、iPodが進化を遂げた「iPhone」が2025年現在のスマホの覇権を握り続けているので、山中先生の先見性は恐ろしいと言わざるを得ません)
これなら胚盤胞(赤ちゃんのもと)を壊す必要もないので倫理面もクリアとなり、ES細胞が禁止されていた国や地域でも爆発的に研究が進みます。
この功績によって山中先生はノーベル賞を受賞したというわけです。

出典:京都大学
もちろんiPS細胞もまだまだ発展途上であり、細胞や組織ごとに作製の難易度は変わります。例えば精子や卵子といったものができるのは当分先の話だと思われます。(倫理規制の影響もありますが)
しかし、いくつかの分野ではかなり良いところまで行ってます。特に発展が目覚ましいのは「眼」「心臓」「血液」「膵臓」の4分野ですね。
これらがこのまま実現に向けて進めば、失明の主原因である病気の治療に役立ち、心臓移植や補助人工心臓に頼らず心不全を治療できる可能性があり、献血なしで輸血を作り出せる可能性があり、糖尿病が薬なしで治療できる日が来るかもしれません。
まさしく革命です🐻❄️
STAP細胞
さてさて、今回の本題であるところのSTAP細胞です。
(正確には「STAP幹細胞」と呼ぶところではありますが、以下では「STAP細胞」に統一します)
ただ、iPS細胞のことさえ知っていれば教養としては十分すぎるくらいなので、ここから先は知らなくとも特に人生には影響しません。なぜならSTAP細胞は存在しないから。
ただ、あの騒動がどういうものだったかを追体験するのには良いと思います。なるべく分かりやすく説明していきます🐻❄️

出典:ウォール・ストリート・ジャーナル日本版
2014年1月30日。
理化学研究所の小保方晴子氏による「STAP細胞の作製に成功した」とする論文が、世界的に権威のある科学雑誌「Nature」に掲載され、日本どころか世界が騒然としました。
その論文の内容は、「細胞を弱酸性の溶液にひたす等、刺激を与えることによって細胞が全能性を取り戻す」というものでした。

さらっと書いてますが、もしこの発見が本当であるとするならばメチャクチャとんでもないイノベーションであり、
iPS細胞はレトロウイルスベクターを用いた遺伝子の導入、適切な培養、その後の選別や確証試験といった、専門設備が潤沢にあってもなお難易度の高い作製方法を経る必要があるのですが、
STAP細胞は酸にちょっと浸けるだけなので、元となる細胞さえ用意できれば高校生が理科室で作れるレベルです。
コストも実用性もiPS細胞を遥かに凌駕するものであり、ノーベル賞を2~3個あげていい超発見と言って差し支えないでしょう。
ちなみにこの時期の私はSTAP細胞のニュースに釘付けで、
大学病院で同期たちと「この発見は歴史を変えるんじゃないか🐻❄️」と毎日のように話していたのを覚えています。
しかしその後、STAP細胞の研究には様々な欠陥が見つかっていくことになりました。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績