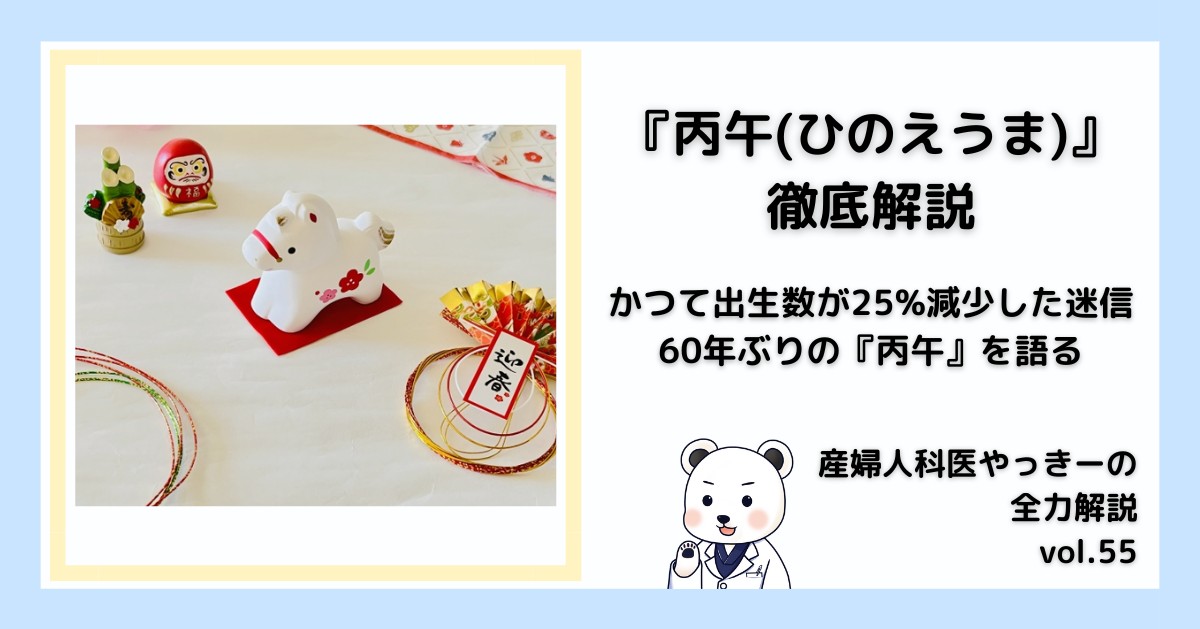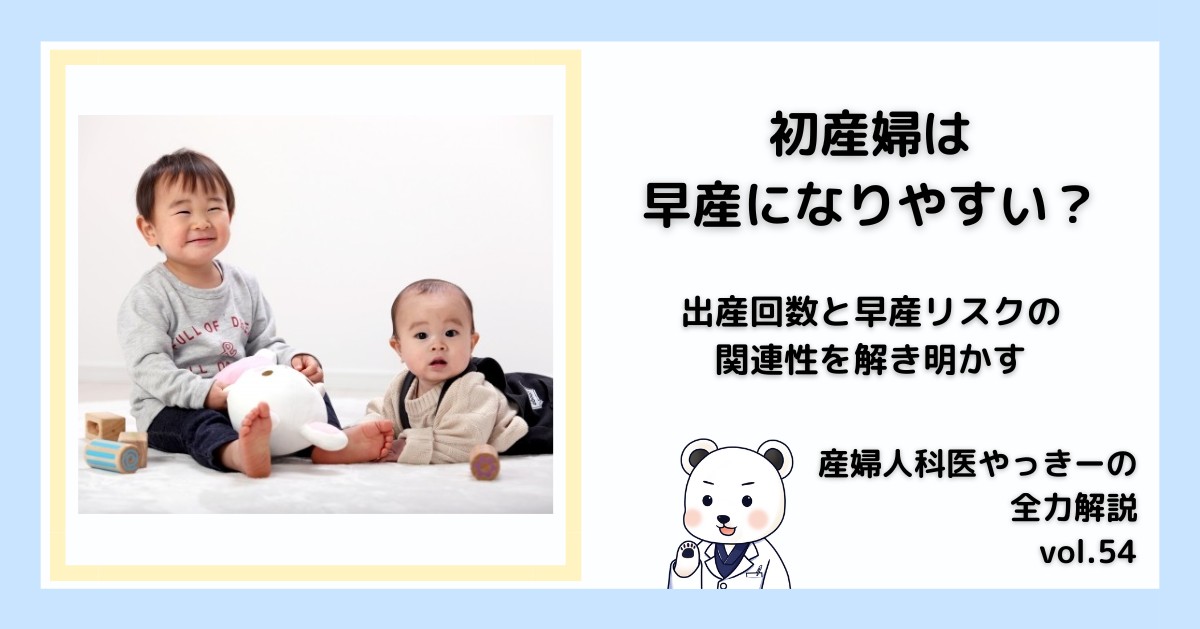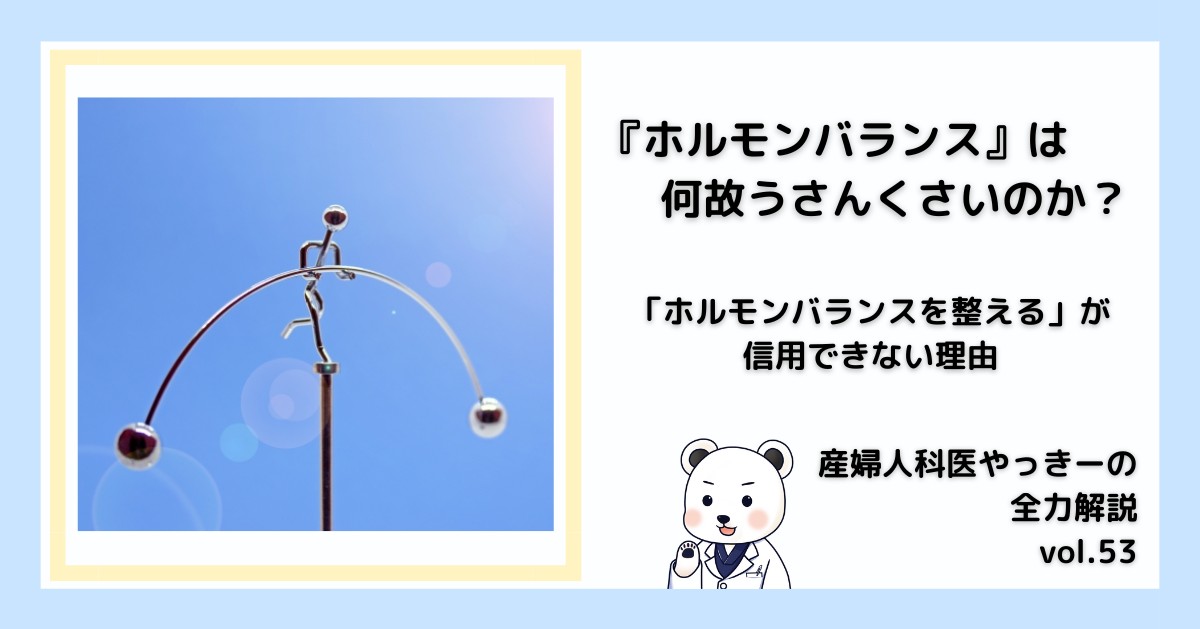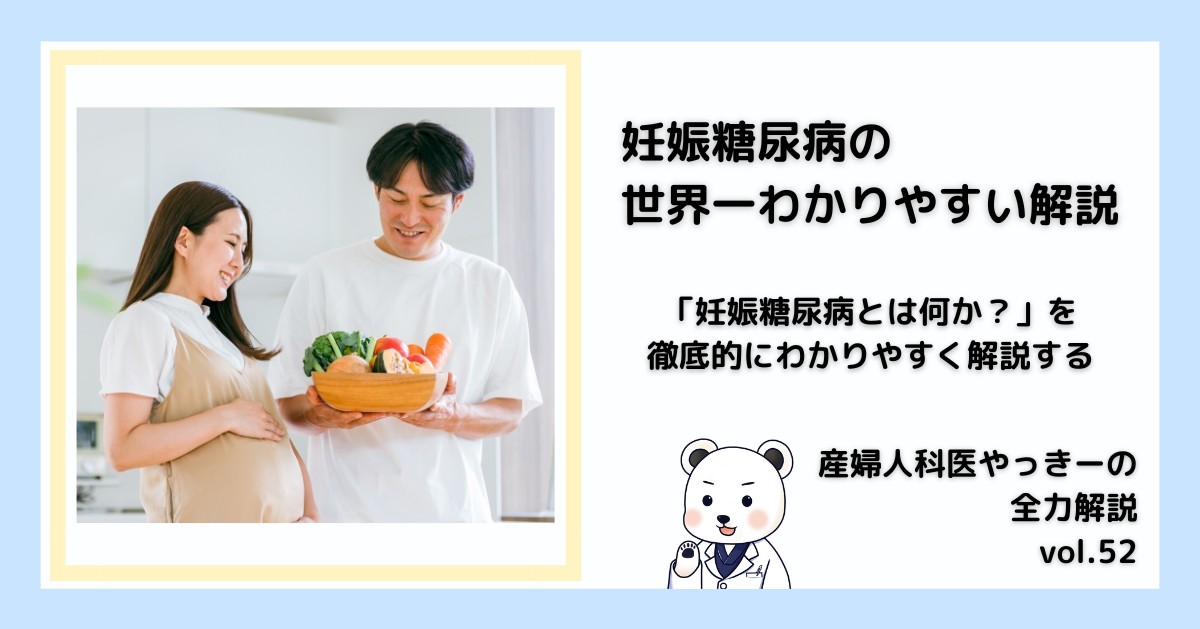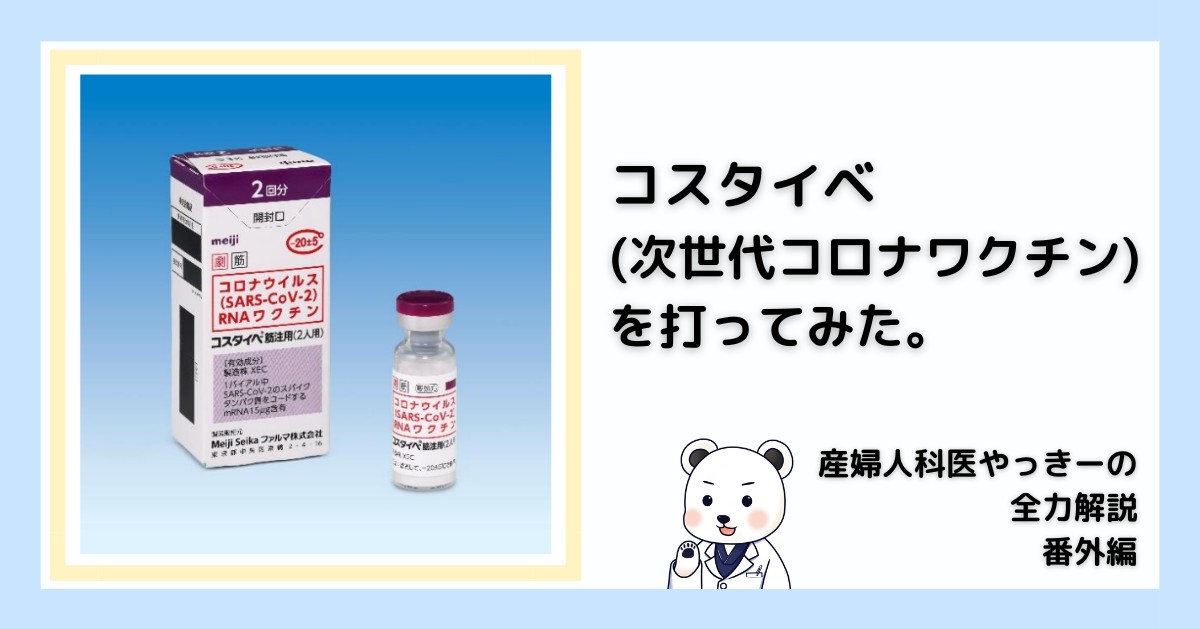全力解説 vol.14「NT肥厚とダウン症の話」

今回のテーマは「NT肥厚」です。
NT肥厚とは、簡単に言えば妊娠初期の胎児にみられることがある首の後ろの厚みのようなものです。
このNTが厚くなっている状態を「NT肥厚」と呼ぶわけですね。
(よく「首の後ろのむくみ」と表現されることがありますが正確ではありません)

出典:市塚清健「妊娠初期超音波計測で重要な数字」周産期医学 53(8): 1177-1180, 2023.
そしてこのNT肥厚は、赤ちゃんのダウン症候群などの染色体疾患との関連性が指摘されている…
…のですが、話はそんな単純なものではなく、
それどころか「NT肥厚があればダウン症の疑い」「NT肥厚があるからNIPTの検査をしましょう」などと言い出す知識が乏しすぎる医者がいますし、
ひどい場合だと、妊婦さん側が何の検査も希望してないのに勝手にNTを測ったり、
NT肥厚を指摘して高額な出生前検査を受けさせようと誘導するゴミかウンコみたいな医者もいます。
そんなわけで本日は「ダウン症候群」と「NT肥厚」についてお話ししましょう。
染色体について
まず、ダウン症候群というのは「染色体異常」に分類される病気なのですが、
そもそも大前提として「DNA」と「遺伝子」と「染色体」の違いがよくわからん、という方のためにここを解説しておきましょうか。
遺伝子やDNAが人間の設計図になっているという認識は一般の方々にもあるかと思いますが、
ここでDNAを「文字」、遺伝子を「文章」、染色体を「本」に例えてみましょう。
遺伝子ひとつひとつの構成要素になっているのが「文字」こと「DNA」です。
もちろんDNAも大事なのですが、文字そのものに意味があるわけではありません。
文字がたくさん集まることで、意味のある「文章」=「遺伝子」になります。

我々の体の細胞はこの「文章」=「遺伝子」を読み取ることにより、必要なタンパク質を合成をするなどの働きができるわけですね。
そんな「文章」が集まることにより、1冊の「本」=「染色体」が出来上がります。

この本の数(染色体の数)は生き物ごとに異なるわけですが、我々人間は基本的に46冊を持っています。
ちなみに「本」=「染色体」は同じタイプの本が2つずつあるといい感じです。上下巻みたいな感じですね。
加えて、46冊のうち2冊はちょっと他とは違う雰囲気の本です。付録みたいなもんです。
というわけで人間が持っている「本」=「染色体」の数は、
44冊(全22巻の上下巻)+付録の2冊で合計46冊になります。
この合計46冊が人間の設計図=ひとつの壮大な物語を作っている、というイメージですね。

なお、本編の44冊を「常染色体」と呼び、付録の2冊を「性染色体」と呼びます。
この性染色体には「X染色体」と「Y染色体」の2種類があり、付録がXとYなら男性、XとXなら女性になるというわけです。
次に、染色体異常についてです。
染色体異常というのは、ダウン症候群などのように「染色体の本数自体がおかしい」「染色体の構造がものすごく変わっている」というタイプの病気です。
遺伝子異常のレベルならば、致命的な疾患を起こす例はそれほど多くありません。
先ほどの本と文章のたとえをそのまま使うと、
本を読んでいて、一部の文章が欠けていたり重複していてもまあそれなりに物語は追えます。

ところが、染色体疾患のレベルになると話は変わってきます。
染色体疾患は「本が1冊多い」「本が1冊足りない」という状況になってくるので、物語自体がうまく追えなくなるのです。
ほとんどの染色体疾患(本が1冊多い・少ない)では赤ちゃんは生存することができず、流産しますが、
ごく一部、胎外生活の可能な染色体疾患が存在します。
そのうちのひとつが「ダウン症候群」(21番目の本が3冊ある)ですね。
このためダウン症候群は「21トリソミー」とも呼ばれます。

出典:国立成育医療センター「ダウン症(ダウン症候群)」
ダウン症候群について
ダウン症候群は発育や精神発達に遅れがみられることが特徴で、
心臓・消化器・甲状腺・視力や聴力にもしばしば何らかの障害が生じます。
もちろん障害者差別などあってはならないのは言うまでもありませんが、
ダウン症候群の児に必要な教育支援や医療ケアは以前よりかなり整備されてきたと言えるものの、それでも育児負担が他の子に比べて少ないとは言えませんし、介護負担の問題は依然として残ったままです。
(児が成人するくらいまでならともかく、親の老後にダウン症患者を支えるための社会的インフラが整っているとは言いがたく、現状では残された兄弟姉妹・親戚の負担が大きい)

そして、このダウン症候群は長らく、産まれるまで診断ができないものでした。
心臓、胃・十二指腸、鼻の形などから、超音波によりある程度の類推はできるものの、診断精度は決して高いとは言えません。
そんな中、羊水検査や絨毛検査などの手法が普及したことで話が変わってきます。
これらの検査によって赤ちゃんが産まれる前に赤ちゃんの染色体を調べられるようになると、
「もし赤ちゃんがダウン症候群だった場合、育児や介護の負担があまりに大きく、経済的な不安もあるため中絶をする」という選択を取られるケースが増えました。
これに関する可否について、私からは言及しません🐻❄️
とはいえ、絨毛検査も羊水検査もそれなりに高額ですし、
どちらも赤ちゃんが居るところに針を刺す検査なので流産などの合併症も懸念されます。
熟練した術者による処置が必要で、「ちょっと採血してみよ」くらいの感覚でできる検査では決してないわけです。

出典:慶應義塾大学病院
そこで「絨毛検査や羊水検査以外に、この赤ちゃんがダウン症候群であるかどうかを判別する方法は無いんだろうか?」
という話になってきました。
しかし、仮にどれだけ高性能な超音波機器で検査を行い、
赤ちゃんの心臓や顔貌などから「この児はダウン症候群の特徴をことごとく満たしている」と診断したとしても、
その赤ちゃんが本当にダウン症であるかどうかは染色体を調べなければなりません。
どんなに高性能な超音波検査をもってしても、「染色体は正常だが、たまたまダウン症候群の特徴と一致していただけ」と区別することはできないためです。
「釘バットを持ち、リーゼントで学ランに【天上天下唯我独尊】と刺繍している男性」を見たとしても、それがすなわち「不良」であるとは言い切れず、
「日曜大工で捨てネコのために小屋を作ってあげることが趣味で、矢沢永吉を愛する敬虔な仏教徒の野球少年」である可能性も否定はできないのと同じですね。

ここでひとつ、用語を解説します。
羊水検査・絨毛検査のように「赤ちゃんの染色体を確実に調べられ、ダウン症かどうかがハッキリする検査」は「確定的検査」と呼ばれ、
超音波検査などのように「赤ちゃんがダウン症かどうかはハッキリ分からないけど、怪しいかどうかをある程度判定できる検査」は「非確定的検査(確率的検査)」と呼ばれています。
お腹の胎児がダウン症候群かどうか調べたいと思っても全例に羊水検査なんてやってたらお金の負担も合併症の懸念もありますから、
羊水検査を行う前に「この人は多少のリスクと引き換えにしてでも羊水検査(確定的検査)を行うに足る妥当性がある」と考えるための判断材料が必要になります。
その判断材料こそが「非確定的検査(確率的検査)」というわけですね。
NIPT(母体血を用いた出生前遺伝学的検査)の話で「非確定的検査」「確率的検査」という言葉がよく出てくるのはこういう意味です。
NIPTについて簡単にご説明しますと、妊娠10週以降に母体の血液検査を行い、母体血中に赤ちゃんのDNAが微量に含まれることを利用して赤ちゃんの染色体異常について調べる手法のことです。

出典:秋田大学医学部附属病院 遺伝子医療部
NIPT自体は赤ちゃんへ危険が及ぶことなく染色体異常について調べられる優れた検査ではあるのですが、
あくまでも染色体異常が「あるかもしれない」「ないかもしれない」という確率が分かるだけであり、
「NIPTで陽性だったからこの赤ちゃんは異常」とか「NIPTで陰性だったから赤ちゃんは大丈夫」と言い切れる性質のものではありません。
さて、ここまでの前提知識を揃えた上で、最初のNT肥厚の話に戻りましょうか。
NT肥厚とダウン症候群の関連、その検査の意味について解説しましょう。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績