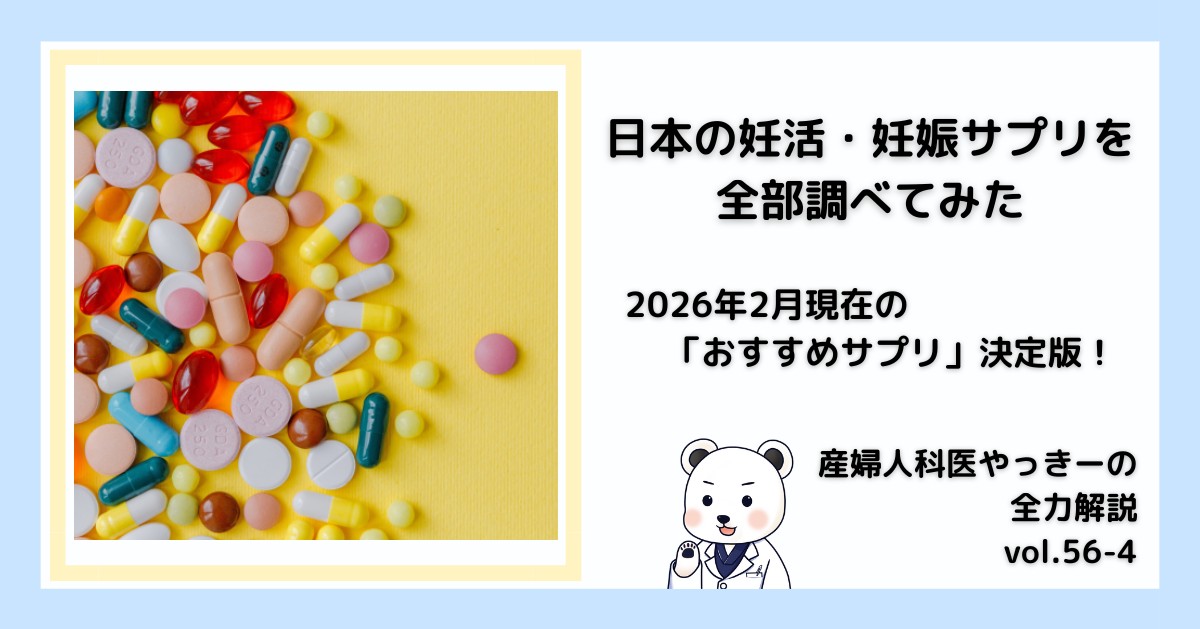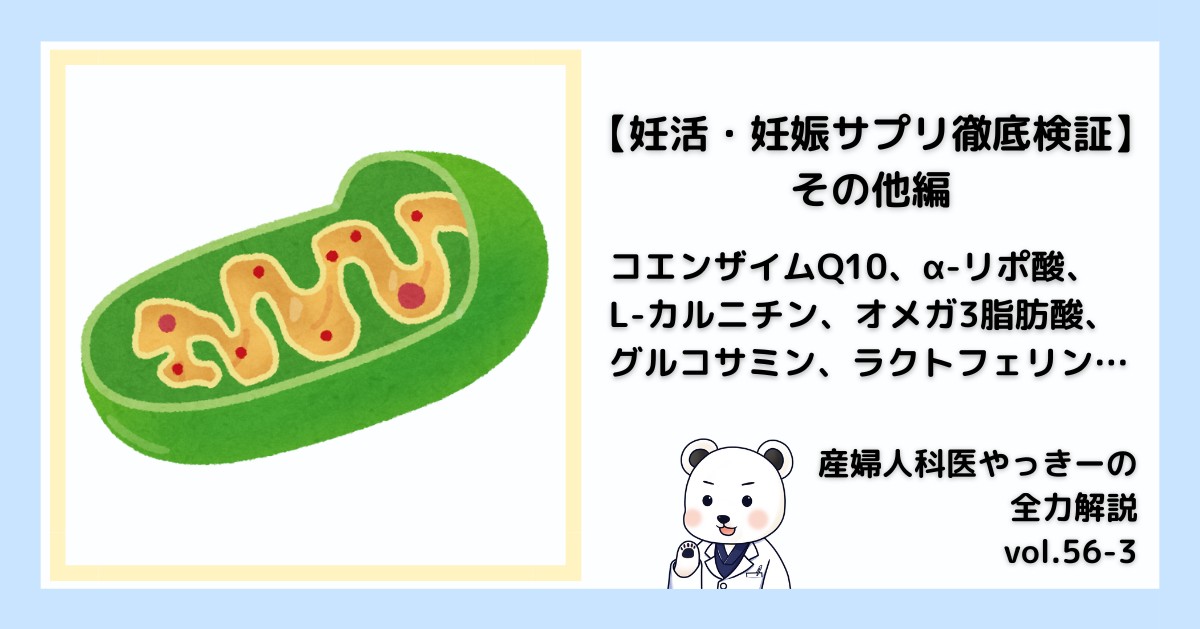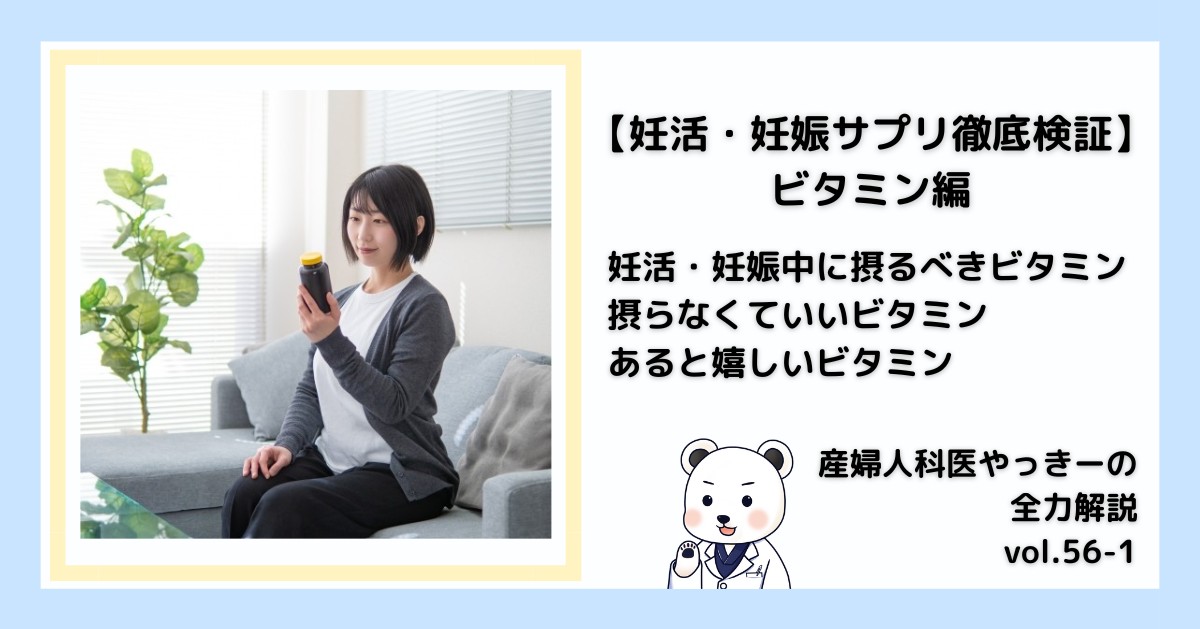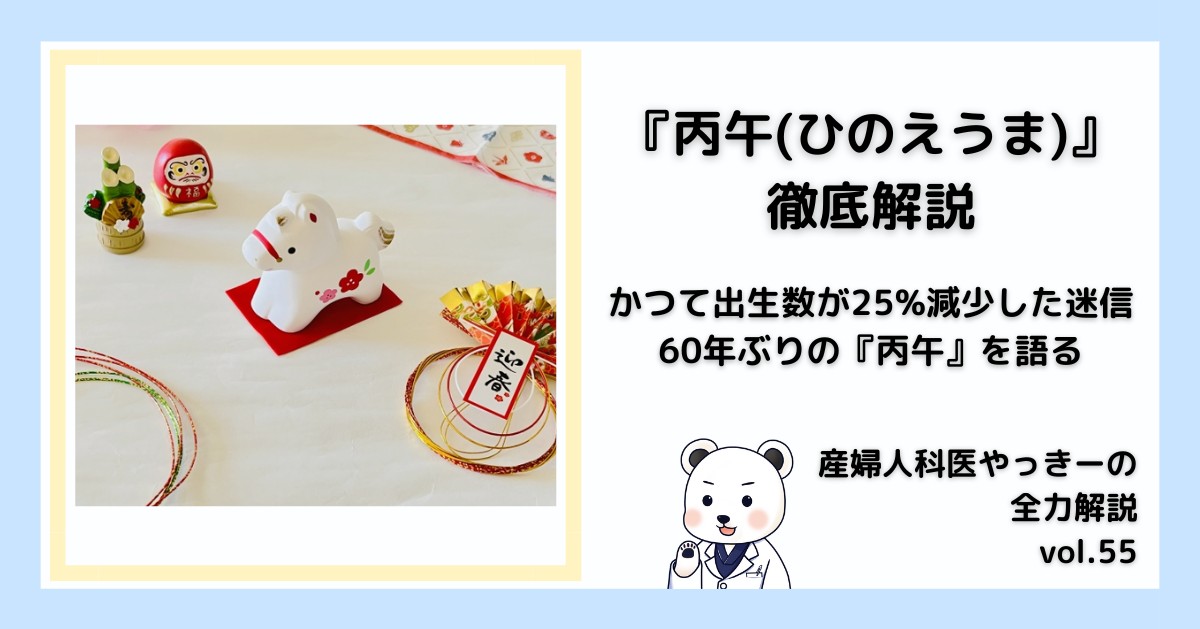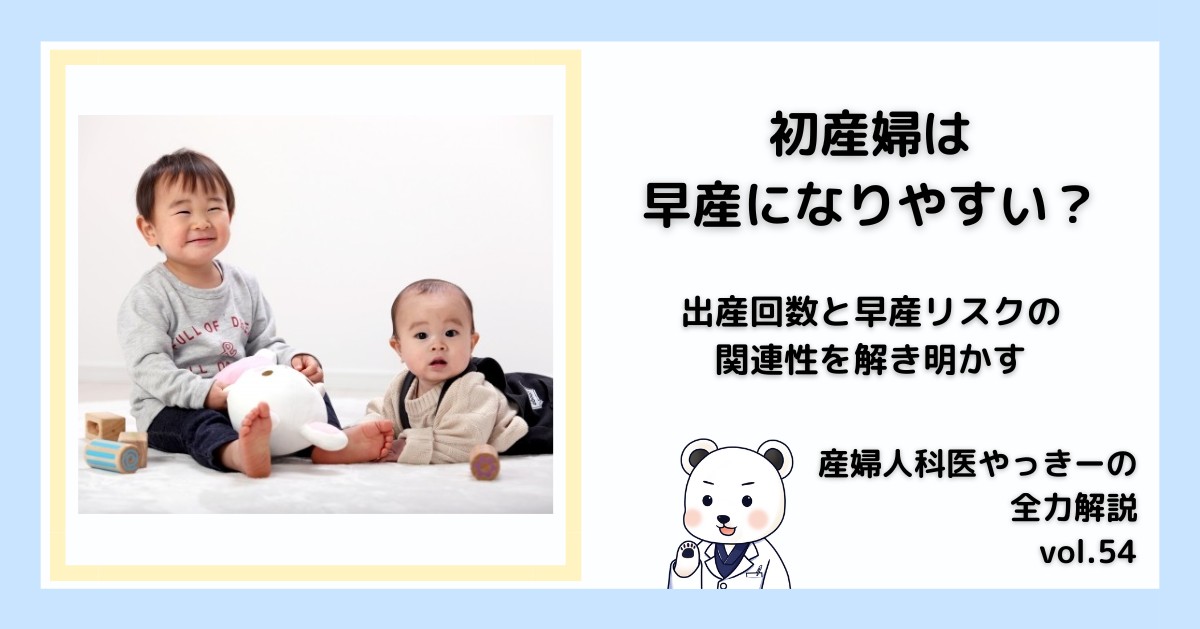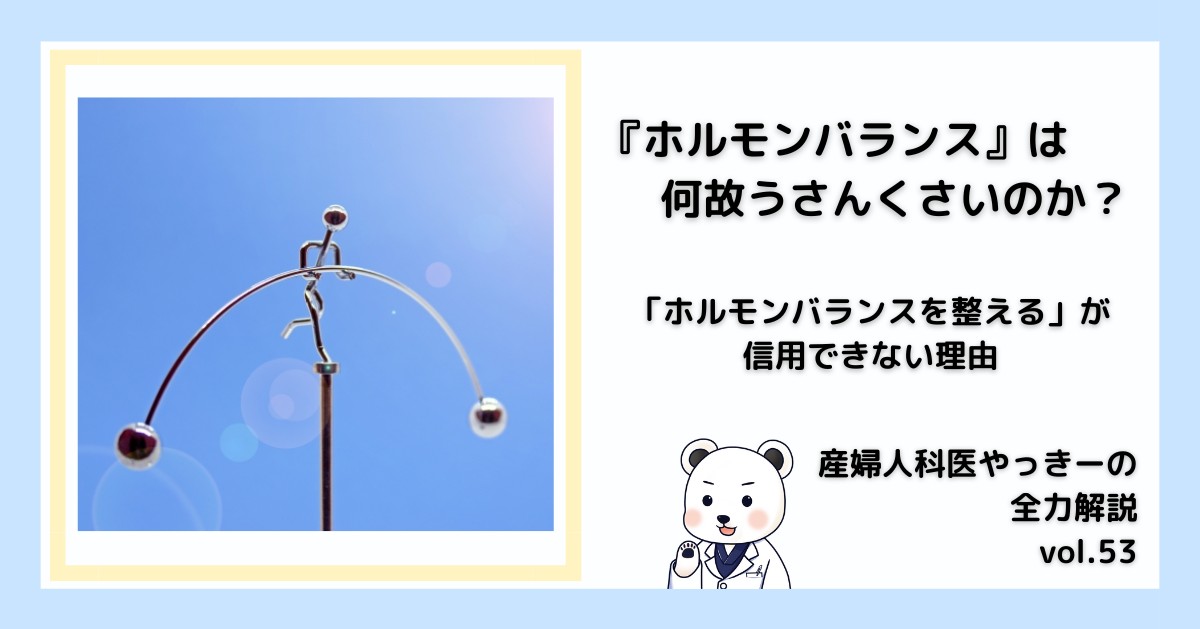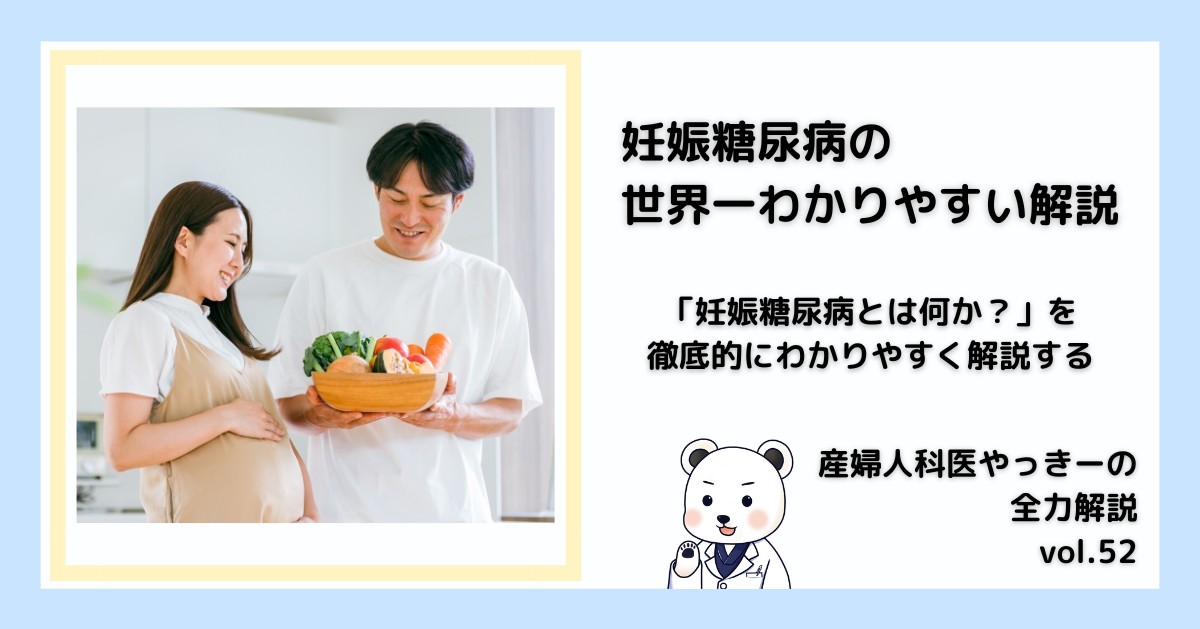全力解説 vol.22「マタ旅についてこれ以上ないほど詳しく調べてみた」

こんにちは!
産婦人科医やっきーです!
本日のテーマは妊娠中の旅行、通称「マタ旅」です🐻❄️
マタ旅といえばSNS上でたびたび炎上騒動が起きることでお馴染みの話題ですね。
どこかの芸能人や一般人が、
「お腹のベビちゃんと一緒に沖縄旅行中だよ~✨」
などと(文面はイメージです)不用意にSNSに投稿し爆発炎上が巻き起こる事件は枚挙に暇がありません。

もはやこの流れは様式美と言っても過言ではないでしょう。
たぶん20~30年後も我らの後継者たちが似たようなことをやっていると思います。
そんな中、2025年1月3日。
新年早々にとんでもない記事が公開され話題を呼びました。
総合情報サイト『PRESIDENT WOMAN Online』にて、
神戸大学病院の感染症内科教授・岩田健太郎氏が
「海外では特別な配慮さえすれば妊娠中の旅行を許可しているにも関わらず、日本の産婦人科医がマタ旅を問題視しているのは合理的な判断とは言えない」
といった趣旨の記事を投稿したことに端を発します。
とはいえ、この話題は我々産婦人科医が2000年前に通過した場所なので、
「今さら何を言ってるんだろう?」としか思わなかったのですが、
ちょうど前回の記事を書き上げたばかりで時間が余っていたので、Xでこの話題について言及してみました。
そしたら思いがけず大反響。
本記事執筆時点で2000リツイート・7000いいねを超える反応が寄せられました。

端的に内容をまとめるならば、
「海外では特別な配慮さえすれば妊娠中の旅行を許可しているのだから、日本の産婦人科医は合理的な判断ができていない」
といったところ。
正直なところ、岩田先生がこのように無理解な記事を書かれたのは残念極まりない。…
我々のようにXのクソリプを栄養素として摂取している産婦人科医からすると、
マタ旅絡みで誰かが炎上する様子はもはやコスられ倒したイベント、略してコスタイベなのですが、
今回に関しては炎上した人・炎上した理由が普段とだいぶ異なる特殊な状況だったので、いつもと違う色の炎が燃え上がっていたぞ、という印象です。
とはいえ、今回の件は記事執筆の良いきっかけになりました。
「何故、マタ旅は勧められないのか」
「海外ではOK(というわけでもないけど)なのに何故日本は妊娠中の旅行に厳しいのか」
といったあたりのことをブログやニュースレターでみっちり解説する機会は今までありませんでしたし、
今回は「マタ旅」について詳しく深堀りしてみましょうか🐻❄️
「マタ旅」の歴史について
言うまでもなく、「妊娠中の旅行」という概念自体は遥か昔から存在しました。
それこそ、聖母マリアがイエス・キリストを出産したのも、
イエスの父ヨセフが妊娠中のマリアを連れてベツレヘムまで110km以上の旅をさせられたことがきっかけです。(観光目的ではなく、皇帝命令による住民登録のためですが)

Bento Coelho da Silveira - "Maria e José buscando guarida em Belém"
このように「妊娠中であろうが何だろうが遠出をしなければならない」というやむにやまれぬ状況は大昔から存在しましたし、
それ故に「妊娠中に不用意に遠出をすることはリスクが高い」という事実も当然、古くから知られていたわけです。
古代中国・隋の時代に書かれた医学書『諸病源候論』にも、妊婦さんの養生法について記載されています。(出典:鈴木千春「中国古代・中世における逐月胎児説の変遷」)
妊娠二月、名曰始膏。无腥辛之物、居必静処、男子勿労、百節皆痛、是謂始蔵也。
(現代語訳例)妊娠2か月目では、生臭(なまぐさ)や刺激物を避けるべき。安静にしておけ。夫は妻を気遣え。体中の関節が痛む。この段階以降、胎児が安定して母体に宿る。
…というわけで、「妊婦さんはムチャしないように」「安静にするように」といった趣旨の言い伝えは1400年前や2000年前から存在していたことが分かりますし、
裏を返せば歴史上において、妊娠中の遠出が良くない結果を生んだ事例も多く存在したことが推測できます。

そんな中、日本はというと、安土桃山時代くらいまでは貴族・支配層以外は自由な行き来が難しく、
せいぜい僧侶が修行や巡礼の目的で旅をする程度だったとされています。
江戸時代に入ってようやく、徳川家康が交通インフラを充実させたことも相まって、
当時の庶民が一生に一度は達成してみたい夢として「お伊勢参り」がブームになったくらいです。
(本来は一般庶民が他の藩に行くことは難しかったものの、お伊勢参りに関しては「宗教上の信仰のため」という名目を掲げることで許されたほか、温泉地へ行く「湯治」も医療行為として認められた)

出典:伊勢神宮
そんなわけで、そもそも江戸時代以前の日本では妊婦さんどころか一般人が遠方に旅行をするということ自体が制度的にきわめて難しく、そうした文化も存在しませんでした。
そして、明治維新や終戦後の高度経済成長期・交通網の発達などを経て、
文化的にも技術的にも「旅行」が庶民にとって身近なものになっていくにつれ、
必然的に「妊娠中の旅行」というものにもニーズが発生します。

そんな妊娠中の旅行を最初に打ち出した人間は誰なのか、手に入る限りの資料を総当たりしてみたところ、
浮上したのは驚きの人物でした。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績