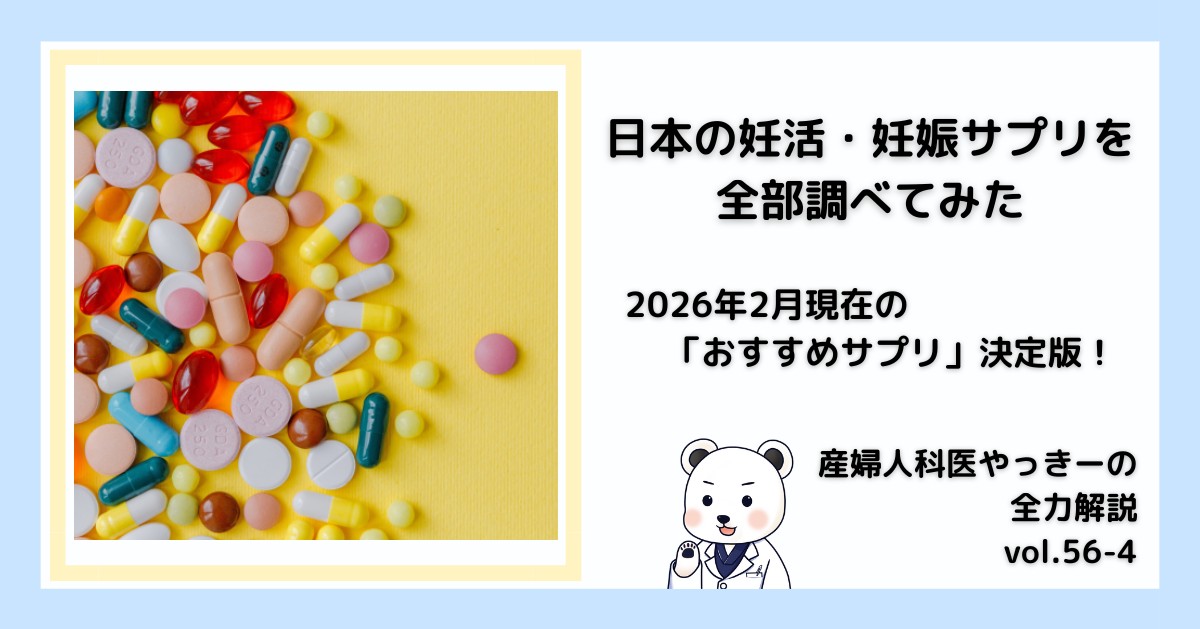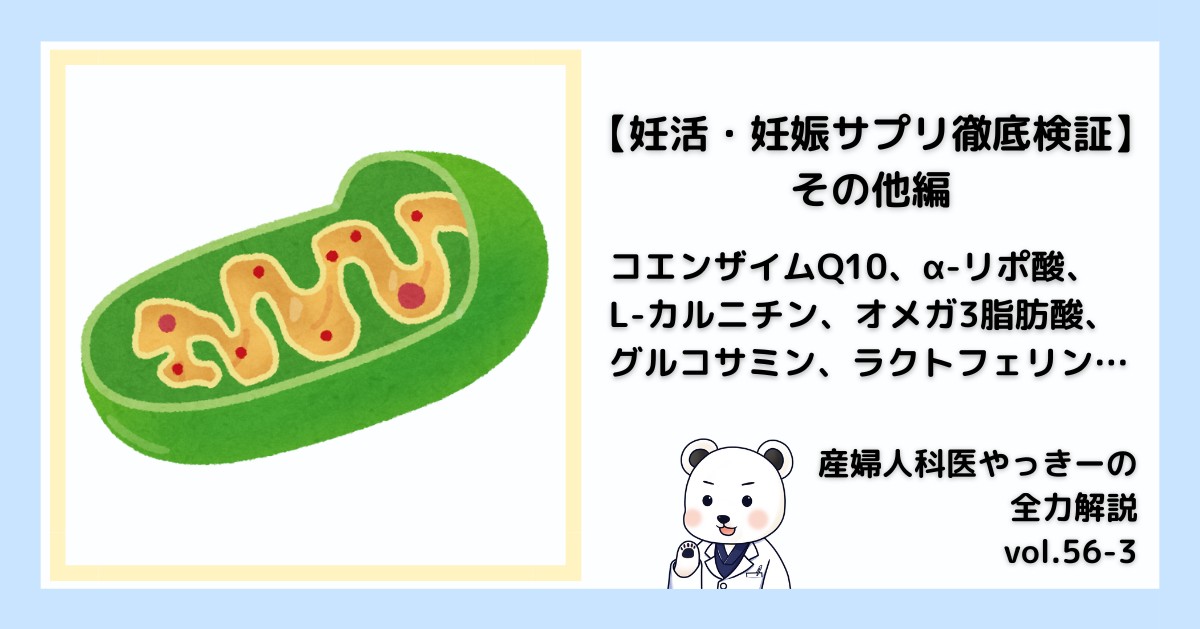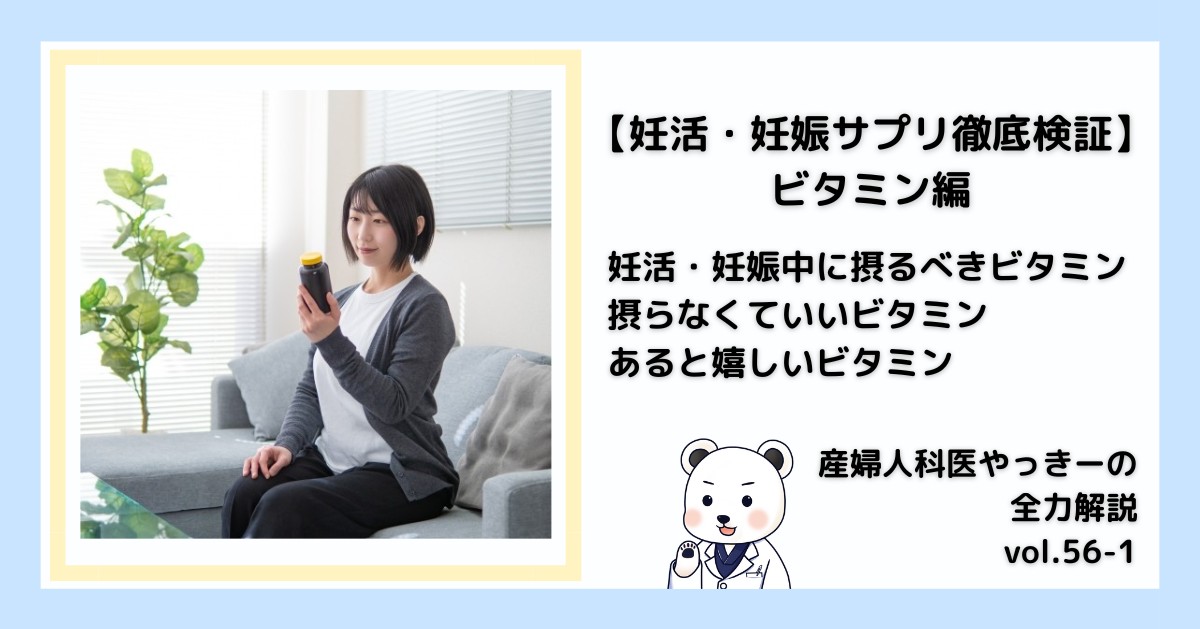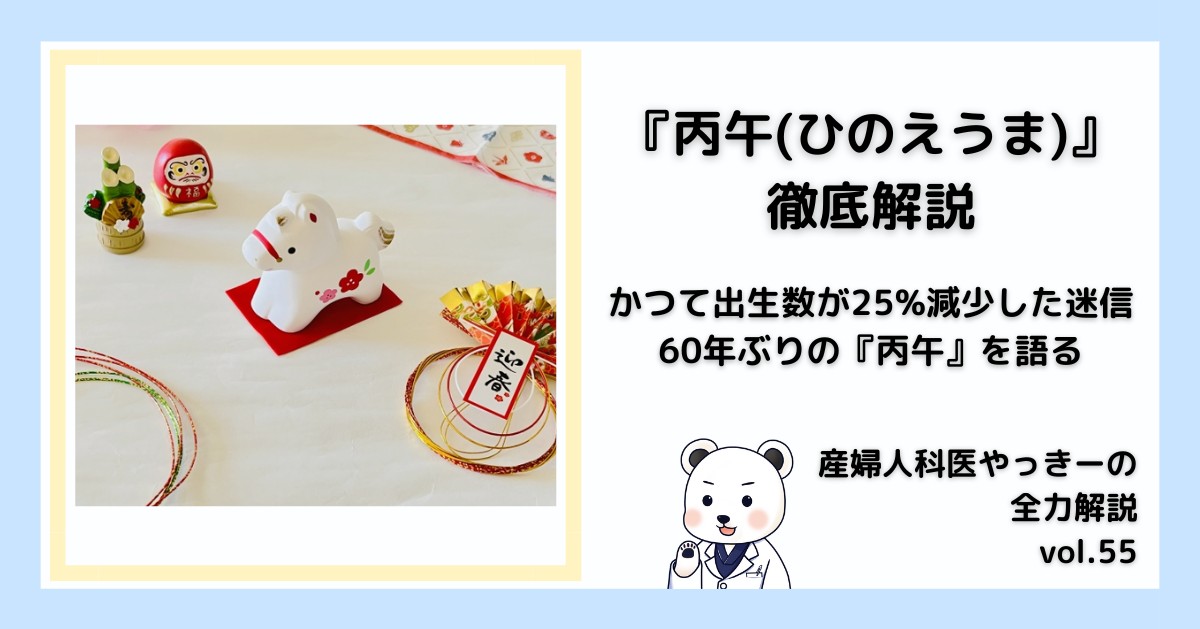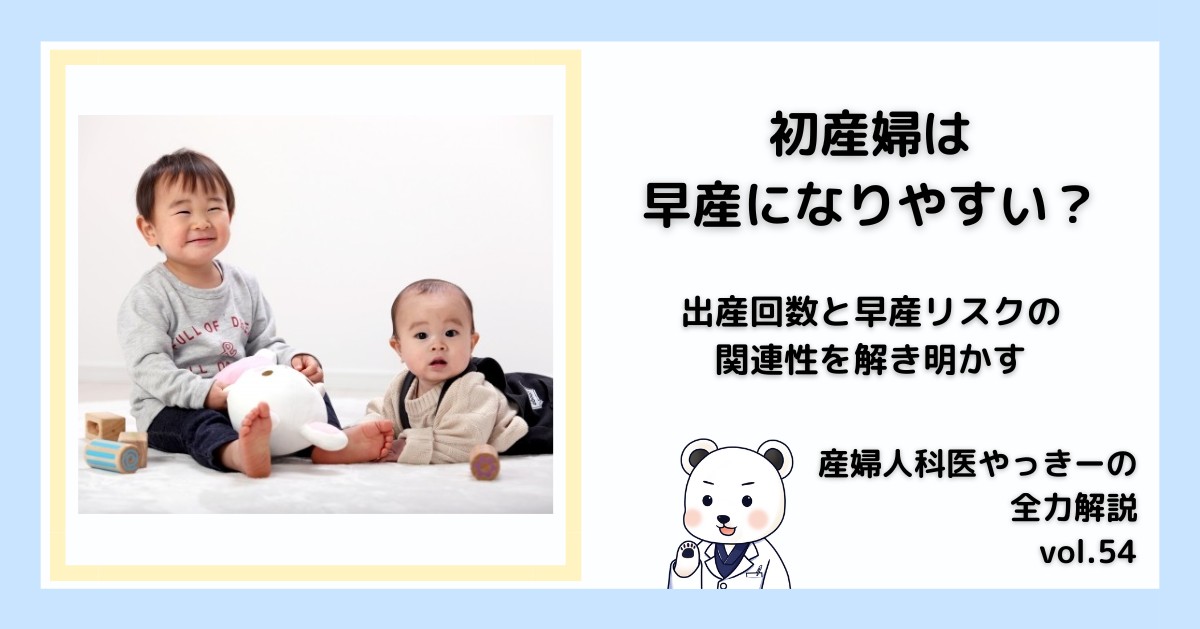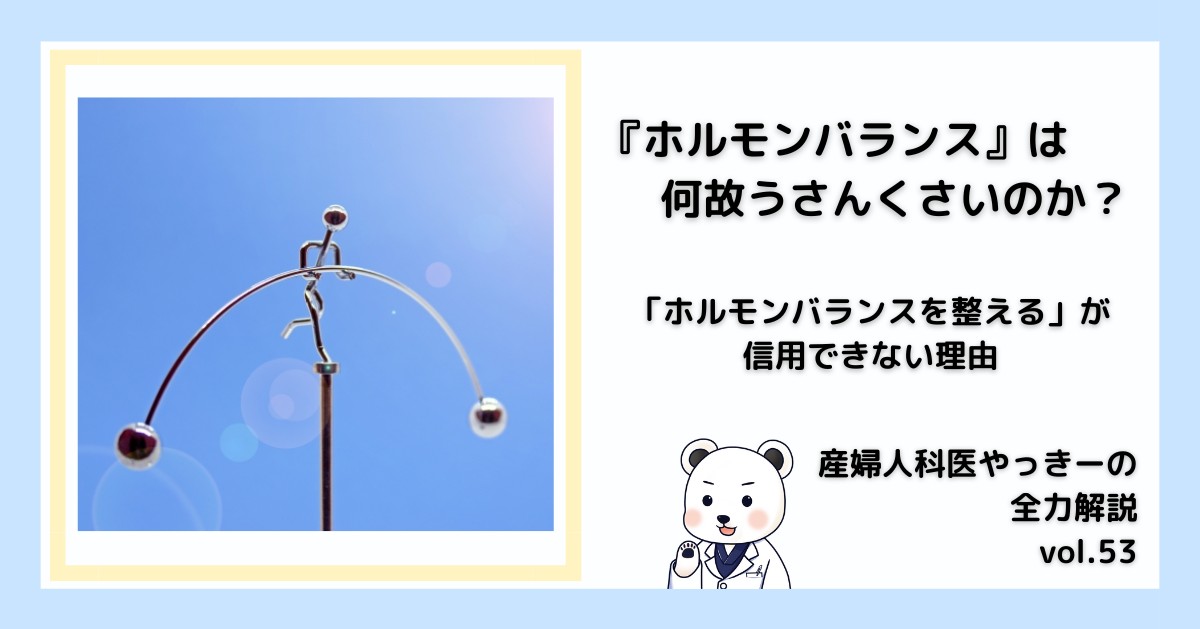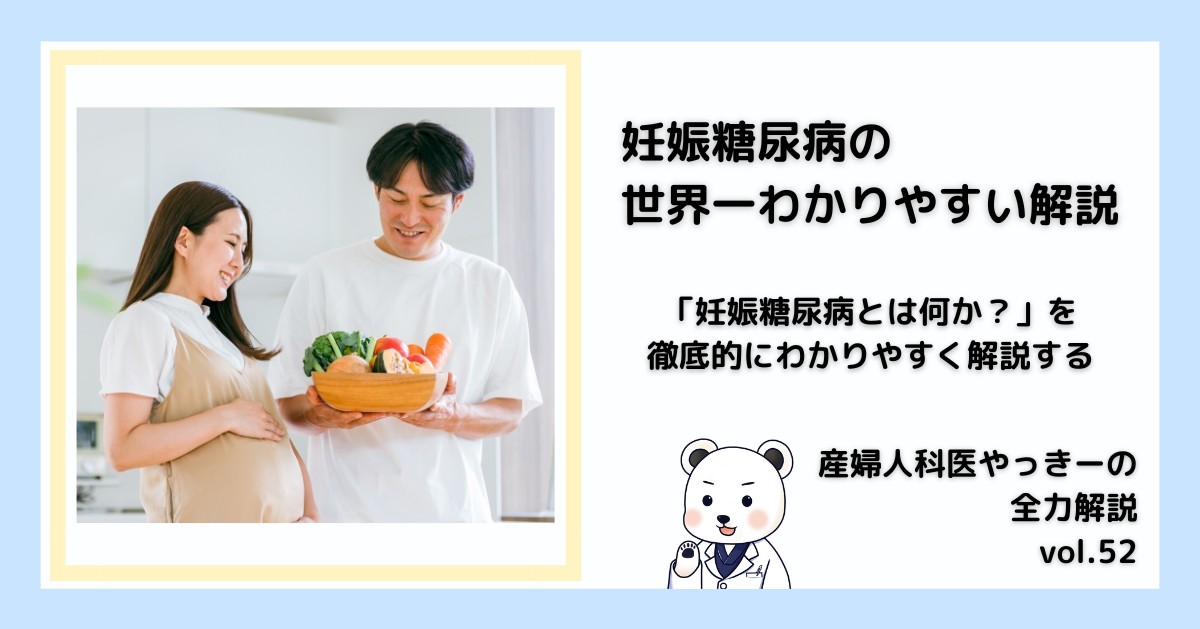全力解説 vol.32「妊娠中の体重管理って厳しくするべきなの?」

こんにちは!
産婦人科医やっきーです!
先日、Xでとある妊婦さんのポストが話題を呼んでいました。
直接引用するのも憚られる内容なので要約して抜粋すると、
🤰「体重管理が厳しいことで有名な某産院で妊婦健診を受けたところ、妊娠前体重+7kgで『食べ過ぎだろ』『バカなの?』『赤ちゃん死んじゃうよ』と罵倒された」
とのこと。
んで調べてみると、東京にある丸の内沿線の某産院をかかったことのある方々から同様の声が非常に多く寄せられており、
口コミの評価はきれいに真っ二つで、「赤ちゃんのためを思ってくれてるのだと感じた」という肯定的な意見もあれば、「デブ」だの「ブタ」だの言われて二度と行かなくなったという意見もあります。
まあ後者に関してはネット上の口コミなので本当にそう言ったかどうかは真偽不明ではあるのですが、そういった声がそこそこ多いのでたぶん実際に言ってると思われます。

この医師の妊婦さんに対する言葉遣いの悪さを一旦置いておくとしても、
体重管理に関する方針はハッキリ言って時代錯誤もいいところで、
さらに医師自身の口の悪さも加味して私なりに評価を付けるとしたらウンコかゴミです。
そりゃ妊婦さんが酒飲んでタバコ吸ってハワイ旅行でキックボクシングして帰ってきましたとか言うんなら「いや何考えてんねーん!!!🐻❄️」と注意されるべきですが、
たかだか数キロの体重増加に対して口汚く罵倒していったい何が解決するというのか。
おまけに、現在さかんに研究が進められている「DOHaD仮説」の観点から考えると、必要以上に厳しい体重制限は赤ちゃんにとって有害となる可能性すらあります。(まだ仮説段階ではありますが)
というわけで本日のテーマは「妊娠中の体重管理って厳しくするべきなの?」です。
妊娠中に体重を増やしすぎた場合・あまり増えなかった場合にどのような弊害が考えられるのか?
体重管理についてどう考えるべきなのか?
赤ちゃんの将来の疾患リスクに影響する「DOHaD仮説」とは何なのか?
やっきーが妊婦健診で行っている体重管理の方針とは?
これらについて解説していきましょう🐻❄️

妊娠中の体重管理に関する変遷
そもそも、「妊娠中に体重を増やしすぎてはならない」と考えられるようになったのは19世紀頃からの話です。
それまでは農業技術の問題で一般市民は太りたくても太れるほど潤沢な食糧がないという状況でしたが、農業や肥料に関する技術革新によって19~20世紀初頭にかけて急激に食料供給が安定します。
したがって、18世紀くらいまでは海外でも「母親が胎児の唯一の栄養源なので、母体は食事を十分に摂るべき」と考えられていましたが、
食料事情が改善する19世紀頃になると、逆に「食べすぎると赤ちゃんが大きくなりすぎて難産になってしまうのでは?」という風潮が生まれ始めます。
ちなみにちょうどこの頃は帝王切開が発明されるかどうかくらいの時期であり、それまでは経腟分娩できないならば母児ともに力尽きて死ぬのを待つしかないという、今以上に出産が命懸けだった時期でもあります。
だからこそ「赤ちゃんの体重を増やしすぎないようにしよう」というのは誇張でなくマジの死活問題だったと言えます。

そんな中、1901年に食事と妊娠に関する世界初の研究が発表され、
「妊娠中の食事制限によって出生体重が男児で400g、女児で500gほど減少できる」ということが示されました。
(今の医学的見地から言うとまあまあ危険な研究なのでマネはせぬように)
その後、母体が食事を過度に制限しすぎるのもそれはそれでよくないことが分かるなど、
すこーしずつ「母体の体重増加は何キロくらいが良いのか」「摂取カロリーはどのくらいか」といった知見が整っていき、今に至っているというわけです🐻❄️
では我らが日本ではどうかと言いますと、江戸時代まではそもそも食糧事情がそれほどよろしくありませんでしたし、
明治~大正にかけて海外の科学が入ってきたことで一時的に豊かにはなりますが、
戦時中~戦後すぐは食糧事情がドン底だったので、体重コントロールや摂取カロリーを気にしている余裕などありませんでした。

出典:毎日新聞
そんな中でも妊婦さんを守るため、「妊娠中は赤ちゃんの分とあわせて2人ぶん食べよう」という俗説が生まれたりしたわけですが、
高度経済成長期を経た食糧事情の急速な改善によってこの俗説が形骸化してからも、1980~1990年代くらいまではまだ「妊婦はとにかく食べるべし」という俗説が存在したことが確認できます。
実際に、1989年に産婦人科医学雑誌に掲載された『妊娠決定時における妊婦栄養指導』(一條元彦. 産科と婦人科 56(4): 576-580, 1989.)において、
『妊娠してしまうといまだに大量の栄養の摂取が必要であると一般に信じられていることも事実である』という記述があります。
こういった風潮を変えた学説として、1990年に米国医学研究所(IOM)が発表したガイドラインのインパクトは大きかったと言えるでしょう。
それまでは、妊娠前の体重にかかわらず一律で「妊娠中は平均〇kgぐらい増えるといいよ」とか「〇kg以上増やさないようにね」といった感じの指針が設けられていたのですが、
このガイドラインで初めて「妊娠前の体格(BMI)に応じて、妊娠中の体重管理の目標値を設定しよう」という動きが生まれます。

出典:Changing national guidelines is not enough: The impact of 1990 IOM recommendations on gestational weight gain among U.S. women
これが分かりやすくもキャッチーな内容で、かつ現場の肌感覚にもわりと近く、
当時の産婦人科医にとっても採用しやすいものでした。
この流れを受けて日本で発表されたのが、1999年の『妊娠中毒症の栄養管理指針』です。
妊娠中毒症(今でいう妊娠高血圧症候群)を予防するため、というごく限定された条件ではありますが、これによって「妊娠中の体重増加量の推奨値」が国内で初めて言及されたわけです。
(ただし設定された数値の根拠が薄かったのでこの指針は2019年に取り下げられました)
さらに2006年に厚生労働省によって発表された『妊産婦のための食生活指針』においても「妊娠中は2人分食べる必要はない」として俗説が真っ向から否定され、
日本の産婦人科ガイドラインにも妊娠中の体重増加量について明記されるなどして現在の目標設定に近付いていった、という経緯があります🐻❄️

体重が増えなさすぎると何が起きるのか?
ここで一旦、具体的な体重増加量に関する話はおいといて、「妊娠中に体重が増えなさすぎると何が起きるのか」を解説しましょう。
現行最新の産婦人科診療ガイドライン(2023)によると「低出生体重児」「早産」のリスクが高まるとしています。
ん?早産?
低栄養だと赤ちゃんが育ちにくいのは分かるとして、なんで早産が増えるんや?
と思われたかもしれません。
まず統計的事実として、2009年の米国医学研究所(IOM)の発表によると、妊娠中の体重増加が基準値よりも少なかった場合は早産率が1.3~1.7倍に増えたとしています。
このようなことが起きる理由は、実のところあんまり解明されてないのですが、
今の時点で「たぶんこうかな」と思われている機序としてはこんな感じ。↓
オカン🤰が栄養不足になる
⇒エケチェン👶「オカンから糖分もらいたいのにあんまり来ないな…自分で糖分作ったろ!」
⇒👶の体内で糖分を増やすためのホルモン(コルチゾール)がたくさん作られる
⇒🤰「むむっこれはコルチゾール!こんなの作れるなんてうちの子は立派に育ったのね…(ホロリ」
⇒👶「え?ワイ糖分足らんから自給自足してただけなんスけど」
⇒🤰「しっかり育ったみたいだし産んだろ!」
⇒👶「オギャー!!」
という感じの説が有力です。
さらに、「低出生体重児」「早産」に加えてもうひとつ「赤ちゃんの将来の健康リスクに影響を与えるかもしれない(DOHaD仮説)」も存在するわけですが、これについては最後に解説します。
体重が増えすぎると何が起きるのか?
では逆に、体重が増えすぎると何が起きるのか?
こちらについても2023年版のガイドラインに明記されておりまして、
基準値を上回った場合に「巨大児」のリスクが1.95倍、「帝王切開分娩」のリスクが1.3倍に増えるという結果が出ています。
ガイドライン外の知見について言うと、2013年にイギリスで発表された研究などで妊娠中の過体重が妊娠高血圧に関連しているという結果も出ています…が、
妊娠高血圧については他の研究も含めて全体的にちょっとエビデンスが弱いかな?という感じで、ガイドラインに載るほどに強力な結果は出ていない状況です。
どちらかと言うと、妊娠高血圧については「妊娠前の肥満が妊娠高血圧の発症リスクと関連している」という知見の方がコンセンサスが整ってる状態ですね🐻❄️
現在の体重増加の推奨値
そして、2025年4月現在における最新版の「妊娠中には何kg増えるのが良いのか」。
産婦人科ガイドラインの内容を抜粋すると以下のようになります↓
妊娠前のBMIが18.5未満 ⇒ 体重増加の目安は12~15kg
妊娠前のBMIが18.5以上、25未満 ⇒ 体重増加の目安は10~13kg
妊娠前のBMIが25以上、30未満 ⇒ 体重増加の目安は7~10kg
妊娠前のBMIが30以上 ⇒ 個別対応(目安は上限5kgまで)
※以上の数値は目安であり、妊娠前の体格に応じて個人差を考慮したゆるやかな指導をする。
この数値は2021年に日本産科婦人科学会周産期委員会が設定したもので、
日本の周産期登録のデータをもとに統計的に「この範囲の体重増加であれば最も合併症が少ない」として算出された目標値ですから、それなりに信憑性は高いものであると言えます。
ちなみに多胎妊娠(双子以上)だともうちょい目標値は高くなるのですが、具体的な数値についてはコンセンサスがまだ取れておりません🐻❄️
体重増加の目安は絶対に守るべきなのか?
ここで冒頭でご紹介したポストに戻りましょう🐻❄️
🤰「体重管理が厳しいことで有名な某産院で妊婦健診を受けたところ、妊娠前体重+7kgで『食べ過ぎだろ』『バカなの?』『赤ちゃん死んじゃうよ』と罵倒された」
ここに出てくる産院をなぜ私がウンコやゴミと形容したかと言いますと、
そこまで厳しく体重管理をする根拠がきわめて薄いためです。

日本産婦人科学会がガイドラインで初めて妊娠中の体重増加の目安について明文化したのは2011年ですが、この時点で既に「厳しい体重管理を行う根拠となるエビデンスが乏しい」ということは明記されていますし、
もちろん現行最新の2023年度版でも同様に「個人差を考慮したゆるやかな指導をする」という方針が推奨されています。
あくまでも妊娠中の栄養管理・食事管理は「バランスの良い食事を摂る」が最優先事項です。体重は目安にすぎません。
どちらかと言うと、この目標設定は「ボディイメージを優先しすぎて妊娠中に十分な栄養を摂らない」「妊娠中に明らかにオーバーな量の食事を摂りすぎる」といった一部の妊婦さんに対する警鐘的な意味合いが強いと思われます。

そもそも論として、妊婦健診で量る体重を私はあんまりアテにしてません。参考にはします。
なぜなら妊婦さんが着てる服や、直前に妊婦さん摂った水分や食事の量、排尿や排便のタイミング次第で体重なんて数百グラム~1キロくらいの単位で変わりうるためです。
(妊娠糖尿病などで通常より厳密なコントロールを求められる場合もありますが)
そんなあやふやなものを重要視するだけならまだしも、「赤ちゃん死んじゃうよ」と脅す所業に至っては医者として…というより人としてカスです。
医者がそんな横柄な態度を取ってもなんとなく世間の風潮で許されてたのはギリギリ昭和までです。
もし読者様の中にそういう医者にかかっている方が居るとしたら、そいつは医学的にも精神的にも令和に全く適応できていない、悪い意味での「お医者様」なので離れることをお勧めします。
さて、ここまでが過去の公式声明やガイドラインにおける「妊娠中の体重増加」の話です。
ここからはちょっと応用編の話として、
「つわりによって減った体重はどのようにカウントすべきなのか?」
「胎児期に低栄養環境に晒された場合、赤ちゃんの将来の生活習慣病リスクが上がる説(DOHaD仮説)」
について、私なりの見解を交えてお話ししていきましょうか。
おまけとして「やっきーは妊婦健診の際にどうやって体重管理の指導をしているのか?」も解説するよ🐻❄️

提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績